[説明・注意書き]
「幼稚舎時代(10歳)の日吉くんが鳳くんに招待されてピアノのコンクールを観にいく話」です。
公式年表にある〈ピアノの発表会〉よりも後の話、という設定にしています。
日(自覚なし)→←(自覚あり)鳳、みたいな感じの両片思いです。
(タイトルは「まじない」と「いわい」の金曜日、です。)
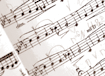
呪と祝の金曜日
「ピアノのコンクールだから正装で行きたい」と話したら、親は袴を出してきた。兄が小学生のときに親戚の結婚式で着たという、日吉家の紋入りの特注品らしい。
なるほど正装には違いないが、スーツやワンピースなど洋装のフォーマルに身を包んだ人々の中では浮いた。大勢の人に二度見され、園児らしいガキには「あのおにいちゃん、テレビの人みたい」と指をさされた(ガキのくせに時代劇でも観ているのか?)。
無難に学校の服でも着てくればよかったと後悔しながら、混雑するコンサートホールの通路を進み、会場に入る。そこは想像よりずっと広く、厳かな空間だったから、俺は少しだけたじろいだ。
学校の講堂の五倍は広さがあるだろう。客席は三階まで続き、壁には教会のそれのようなフレスコ画が描かれている。どでかいステージには真紅のカーテンがかかり、天井からつるされたシャンデリアの明かりがそれを照らす。ますますもって袴が似合う場所ではない。
ピアノの「発表会」には以前も招待されたことがあるが、「コンクール」は今回が初めてだ。出場者の鳳いわく「地域レベルの小規模な」ものらしいが、その話が本当なら全国規模のコンクールでは東京ドームにでも行くことになるんだろうか。
招待状に記された席番号は、前から十列目のどまんなかという、特等席にあたるだろう座席を示していた。生地が張らないように袴を持ち上げながら座ると、驚くほどやわらかなクッションの感触が俺の身を包んだ。
***
一週間前の金曜日。昼休みの音楽室で、俺は奇妙なモノを見た。
「なんだ、それ。おまえ、筆箱の中にそんなもん入れてんのか?」
ピアノのイスに座った鳳が筆箱を開いた瞬間に、目に入ってきた違和感。手をのばしてそれを持ち上げると、鳳は「あっ」と声を発し、隠していた答案用紙を発見された問題児のような顔になった。
「木の枝……だよな? これ」
それは俺の手に収まるサイズの小枝だった。いまの季節、外に出ればそこらじゅうの道端に散らばっていそうなモノだ。
「あ。もしかして木の枝に見せかけたペン、だったりするのか」
こじゃれた雑貨屋とかに行けば、そういう商品もありそうだ。と思ったけれど、鳳は「ううん」と首を横に振った。
「それは……おまじない、みたいな」
「おまじない?」
「きれいな枝をひろって筆箱に入れておくと、大事なときに勇気を出せるようになるって。ピアノの友だちから聞いて」
「ふーん、なるほどな。で、効果はあったのか?」
「えっ」
質問を重ねた俺の前で、鳳は意外そうに目をまるくした。
「なんだよ、その反応」
「だって、日吉くんはこういうの興味ないかなって……。バカにされそうだから黙ってたのに」
「……失礼だな、おまえ」
低めの声で凄んでやる。鳳はあわてた様子で「ごっ、ごめん」と手を合わせた。
「俺だって興味あるぞ。おまじないって、要は呪術の一種だろ? 字も同じだしな」
鳳の筆箱から鉛筆を一本取って、手元に持っていた本のブックカバーに〈呪い〉と書きつける。鳳はその文字を見て、「え?」と首をかしげた。
「これって、“のろい”じゃないの?」
「“のろい”とも読むけど、“まじない”とも読むんだよ」
「えっ、そうなんだ! 日吉くん、やっぱり物知りだね。ボク、ぜんぜん知らなかったよ」
キラキラした顔の鳳から尊敬のまなざしを向けられて、俺はうっかり鼻が高くなる。気分をよくした俺が呪術の起源やら現代のシャーマニズムやらについて語っているあいだも、鳳は感心したような声でしきりに相槌を打っていた。
「日吉くんって、ヘンなこといっぱい知ってるね」
という褒め言葉は、やっぱり失礼だったけど。
気がすむまで話し終えると、昼休みは残り五分になっていた。そろそろ教室に戻るかと考えて手荷物をまとめ始めたところで、ふいに「あのっ!」と不自然な大声が上がる。
「なんだよ、急に」
「……えっと」
鳳はためらうみたいに口ごもった。かと思えば次の瞬間、
「……実はもういっこピアノの友だちのあいだで流行ってるおまじないがあって!」
と、たたみかけるように言って俺のほうに身を乗り出してきた。
「その……ピアノの楽譜に好きな人からメッセージを書いてもらうと、コンクールの日にうまく演奏できる、っていう……」
「……好きな人、って。おまえ、そういううわついた話もするタイプだったんだな」
“おまじない”よりも、そっちのほうが意外で気を取られた。鳳は一瞬、ぽかんと口をあけて固まったあと、おもしろいくらい露骨に顔を赤くした。
「違っ……そういうことじゃなくて! 好きな人って『大好きなお母さん』とか『大好きなお友だち』とかそういう意味で!」
「焦りすぎだろ、おまえ」
「だ、だって日吉くんがヘンなこと言うから……」
りんごみたいにほっぺたを丸く赤くした鳳の腕の中で、革張りの楽譜カバーにシワが寄っていた。半月くらい前から、鳳は昼休みのたびにこの楽譜を持って俺をコンクールのための練習に付き合わせてきたのだった。
フン、と鼻から息が抜けた。腹が立ったりしたのではなく、むしろ反対の作用で。
「おまえ、俺にそれを書いてほしいって言ってるのか?」
答えを知りながら問いかけた俺の前で、鳳は「うん」とも「ううん」とも言わず(つまり「うん」って意味だ)、無言で俺に楽譜を差し出した。受け取ると、なめらかな革のカバーは手のひらに優しくふれてきた。
「……こんどのコンクール、ボクが出るのは『十歳から十三歳の部』なんだけどね」
「ふうん」
「いちばん年上の人は中学二年生だし、ボクより長くピアノを習ってる先輩がほとんどで……。同じ十歳の友だちも、みんなすごく上手な子だし」
「ようするに、自分より強そうなヤツばっかりで不安、って話だな?」
生まれてこのかた家の中で兄に負かされ続け、道場で上級生に負かされ続けている俺にとっては、そんな状況は日常茶飯事だ。だけど、いかにもおぼっちゃん育ちっぽいコイツにとってはそうじゃないんだろう。
「いいぜ。書いてやる」
「えっ、ほんと!?」
「ピアノのことはよくわかんねーけど、十歳から十三歳の部、って十歳にはだいぶ不利でハラ立つしな。俺の下剋上パワーを分けてやるよ」
「……うん!」
鳳はまたキラキラの顔になって、俺に鉛筆を持たせた。俺はしばらく『亜麻色の髪の乙女』と題された楽譜の余白を見つめてから、とめ・はね・はらいを意識して文字を書き込んでいった。
“下剋上等! 日吉 若”
それはわれながら力強く、凛とした文字だった。俺の“おまじない”がかかった楽譜を受け取ると、鳳は満開の桜みたいに顔をほころばせた。
「ありがとう、日吉くん……! ボク、すっごくうれしい!」
桜色になった鳳は、ニコニコしながら言葉を続けた。
「発表会とかコンクールって、暗譜じゃないとダメなときもあるんだけどね」
「あんぷ?」
「楽譜を見ないで演奏することを、暗譜、っていうんだ。でも今度のコンクールは楽譜の持ち込みもできるから、ボク当日も絶対、この文字を見ながら弾くよ!」
うれしい、幸せ、大好き、って堂々と書いてあるような笑顔だった。さすがに照れくさくなって、俺は話をそらした。
「そっ、そういえば、コンクールの当日っていつなんだ?」
「えっと、つぎの祝日の日だよ。来週の金曜日……」
少し迷うように黙ってから、鳳は言葉をついだ。
「この前の発表会とは違う会場で、ちょっと遠いんだけど……日吉くん、よかったらまた見にきてくれる?」
「ん~、どうするかな。俺、そろばん教室の宿題もあるし、道場で稽古もしたいし……」
「……あ、そっか、そうだよね。いそがしいもんね、日吉くん」
ムダにもったいぶっただけの俺の言葉を、鳳はかんたんに真に受けてしょげた。コイツがいつもこんなふうだから、俺はいつのまにか、イジワルを楽しいと感じるような男になってしまっていた。
「まぁでも、せっかくだから行ってやる」
「ほんとっ?」
「そのかわり、おまえ絶対優勝しろよ。俺がわざわざ見にいくんだから」
「えっ……そ、それはちょっと、むずかしいかもしれないけど……」
いつもの気弱な調子で言ってから、鳳は楽譜を胸に持ち、すっくと立ち上がった。
「……でも絶対、全力でがんばるよ。ボクも日吉くんみたいに下剋上する!」
「おう、その意気だ」
ガラにもなく拳を突き上げた鳳の頭上のスピーカーから、昼休みの終了を告げるチャイムが流れてくる。その日、俺は今年初めて授業に遅刻した。
***
きっと緊張しているに違いない、と思っていた。だけど審査員や大勢の観客の視線を一身に浴びながら出てきた鳳は、意外にも落ちついた足どりで広いステージの中央へと歩いていった。
アナウンスの声が彼の名前を読み上げ、演奏曲の紹介をする。その声が終わると、鳳は客席に向かって一礼し、拍手を受けながら巨大なグランドピアノに近づいた。
穏やかな所作でイスに腰かけた鳳は、前回の発表会のときに着ていたのとは違う、明るいグレーのスーツに身を包んでいた。ひざ丈の半ズボンに、上品な茶色のネクタイ、おとなが履くような立派な革靴。袴を着た俺とは正反対の、パブリックスクールの生徒然とした西洋的な雰囲気は、この会場にも鳳自身にもよく似合う。アイツの見てくれをかっこいいなんて思ったことは一度もないが、しかし俺の審美眼は決してバカではないので、それが客観的にみて美しいものだということは理解できた。
学校の女子とかが見たら騒ぐだろう。っていうか、男子も騒ぐかもしれない。鳳は男女ともに人気が高い。人気、というより八方美人の結果としての俗受け、だと俺は思うが、鳳の周囲には常に、アイツ自身と似た、フ抜けて無害そうな連中が集まっている。
——だけど今、この席に座っているのは俺だ。
おごった気分にひたった瞬間、ステージの上の鳳と目が合った——ような気がした。前から十列目とはいえ、ステージの中央まではかなりの距離があるから、錯覚だろうけど。
鳳は例の革張りの楽譜カバーを開き、譜面台に置くと、数秒ほど楽譜を見つめてから演奏を始めた。昼休みの音楽室で何回も、何十回も聴かされた前奏曲が始まる。
飽きるほど耳にしたはずのその曲は、でも俺に違和感をもたらした。原因はこの会場だった。学校の音楽室よりずっと広く、高性能の音響設備を備えているんだろう空間の中で、聴きなれた音色は聴きなれたものとして俺の耳に落ちてきてはくれなかった。
——なんか、音楽室で聴くほうがいいな。
だけど会場特有の音の広がりや反響に慣れてくると、その中心にはやっぱり俺の耳になじんだ、鳳の演奏の手つきがあることもわかった。俺は音楽のことなんて知らないし、巧拙の判断はできないけれど、聴いていて単純に快い音だった。これまでに聴いた他の出場者の演奏よりも「いいもの」なんじゃないかという予感がした。その予感が正しいものだったとわかったのは、すべての曲の演奏が終わり、最後の音の余韻が消えた瞬間だ。
静けさが、澄んだ。会場じゅうの観客の意識が合わさってひとりの巨人になり、言葉をなくして息をのむように。悔しいけれど俺もその巨人の一部だった。
やがて巨人は個々の人間に戻り、それぞれに感嘆の息をついた。楽譜を持って立ち上がった鳳が客席に向かって礼をすると、拍手が起こった。他の出場者のときのような盛大な拍手ではない。それは人肌にあたためた、ホール一杯ぶんの白い綿毛を彼に浴びせるような手のひらの音だった。
祝福めいたその音の均衡を壊してしまわないように、そっと手をたたく。それから約一時間、他の出場者の演奏が続き、その後休憩を挟んで「十歳から十三歳の部」の審査結果の発表になった。
——あの演奏が入賞しないわけがない。
そう思ったけれど、ステージのすみっこで緊張顔になった鳳はなかなか名前を呼ばれなかった。審査員特別賞、協会賞、奨励賞、技能賞、銅賞……と読み上げられる賞のランクが上がっていくにつれ、鳳の顔が青ざめていく。その顔を見ていたら、俺の胸にまで不安がしのびこんできた。
——くそ、弱気になってるんじゃねえよ。
鳳に、そして自分自身に内心でカツを入れる。「銀賞」として呼ばれた二人の中にも鳳の名前はなく、鳳はほとんど泣きそうな顔になった。だから「金賞」が発表されたとき、彼は緊張の鎖を解かれて放心するようなダサい表情をみせた。——とびっきりの晴れ舞台だっていうのに。
三回目の拍手の音に包まれてステージの中央へと進んだ鳳の手に、金色のトロフィーが渡される。司会者からマイクを向けられた鳳は、
「ありがとうございます、とてもうれしいです。応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました」
と、ビビるほどおもしろみのないコメントを残して客席に頭を下げた。
あいかわらず優等生のお手本みたいなヤツだ。——俺の前では、ときどき妙ににくたらしい顔をするくせに。
気づくと俺は笑っていた。毎日昼食のついでに練習を聴いていただけなのに、自分のことみたいに気分がよくなってしまった。ステージ上でずらりと横並びになった受賞者たちの、いちばん真ん中で、鳳はトロフィーを抱きしめるように抱え持っていた。鳳の両隣に立っている「銀賞」の受賞者は、二人とも鳳より頭ひとつぶん以上も背が高かった。おそらく中学生だろう。
——すげぇ。俺の“おまじない”で、本当に下剋上だ。
もちろんそんなモノはほんの願掛けにすぎず、鳳自身の努力が実を結んだ結果だということはわかっている。けれど、彼の成果を勝手に誇らしく感じてしまう気持ちは急速に俺の胸に注ぎ、いつまでも引いていかなかった。
***
結果発表後の十五時半に、会場のロビーで待ち合わせる約束だった。時間ぴったりにロビーに着くと、鳳は笑顔で手を振りながら通路を走ってきた。
「お……」
おめでとう——って言いかけた俺の声に、鳳の大声が割り込む。
「日吉くん、その和服すっごくかっこいいねー! ボク、ステージの上からでもすぐに見つけられたよ!」
——いや、今そんなのどうでもいいだろ……。
あきれた俺の前で、鳳はなおも俺の袴姿を褒めちぎり続け、そしてどうにもナマイキなひとことで賛辞をしめくくった。
「ありがとう、ボクのために着てきてくれて」
「いや、べつにおまえのためとかじゃねーし。うぬぼれんな」
「え~……でもこのコンクールがあったから、わざわざ着てくれたんでしょ?」
金賞でテンションが上がっているのか、鳳は俺の否定も意に介さず、俺の手を取って通路を歩き始めた。
「あっちに出場者用の控え室があるんだ。そこに荷物を置いてあるから、それ取ったらいっしょに帰ろ!」
「荷物って、あのトロフィーもか?」
「あれはお父さんたちに渡して、先に車で持って帰ってもらったよ。歩いて持って帰るのはさすがに重いし、ちょっと恥ずかしいから」
「ふうん」
会場の裏にあるという控え室に近づくと、ロビーにいる人々のざわめきが遠ざかり、空間が静けさに包まれていった。間接照明だけが灯るうすぐらい廊下には、白いドアが等間隔に並んでいた。〈控え室・10歳〉というゴシック体の文字をのせた紙が貼られたドアは、廊下に向かって十センチくらい開放され、そのすきまから室内の明かりがもれてきていた。
「じゃあボク、すぐに荷物を取っ——」
ドアノブに手をかけた鳳の声は、不自然なところで切れた。
「おい、どうしたんだよ」
鳳はドアのすきまから室内を見ていた。さっきステージで青ざめていたときの何倍も、顔面蒼白、って感じの顔をして。気になって後ろからのぞきこむと、室内には人の姿があった。
ここは十歳の控え室らしいから、俺たちと同い年のヤツだろうか。紺色のスーツに身を包んだその男子は、部屋のすみで見覚えのある楽譜を手にして立っていた。
「あれって、鳳の楽譜……」
なんで、と続けかけた声が引っこむ。思いつめたような顔で楽譜を見下ろしているそいつの右手に、太い油性ペンが握られているのが見えたからだ。
ペンのキャップは外され、ペン先は惑いながらも楽譜へ近づこうとしていた。俺の頭は怒りでカッと熱くなり、俺の足は迷わず室内へ進もうとした——けれどその瞬間、鳳の手が俺の手首をつかんで引っぱった。ドアから遠ざけるように、面食らうほど強い力で。
「おい、何すんだっ……」
反対側の壁まで俺を引っぱっていった鳳は、ひどくこわばった顔で俺を見た。そして室内のアイツを気にしてか、蚊の鳴くような小声で話し始める。
「あ、……あの子、ボクの友だちで。小枝のおまじない、教えてくれた子で」
「だから何だよ。アイツ、どう見てもおまえの楽譜をめちゃくちゃにしようとしてるだろ」
ここからはドアのすきまは見えず、室内の様子はわからなかった。もしかしたらあのペンはすでに楽譜に届き、紙面を真っ黒に塗りつぶしているのかもしれない。そんな状況なのに、鳳の手の力はいっこうに弱まらなかった。俺の手首を拘束したまま、鳳は泣く寸前のように眉を波打たせた。
「あの子の家、いまお父さんが入院してて」
「……は?」
「あしたが手術の日、なんだって。だから手術の前にコンクールのトロフィーを見せてあげるんだって、ずっと話してて」
でも——と続けた鳳の声は、もう完全に水気で濁っていた。
「でも、あの子は入賞できなかったから……。きっと今、すっごくつらいんだと思う」
「だからって、おまえにやつあたりをしていい理由にはならないだろ」
「そうだけど……いつもは絶対あんなことをする子じゃないんだよ、本当に。だから」
「だから?」
萎縮しきった鳳の顔を見ながら、俺のはらわたはふつふつと煮え始めていた。追及のように問いかけた俺の前で、鳳はいよいよ涙を流してうつむいた。
「……ボク、あの子と気まずくなったりしたくないから」
ぽた、と涙が足元に落ちる。純度百パーセントの優しさによって流されたんだろうその涙を見て、俺はさらに激しい怒りで燃えた。体が火になったみたいに、燃えた。
「なんだよ、それ。おまえ、それで優しいつもりかよ? 友だちだったら、間違いは間違いだってちゃんと言ってやるべきじゃねぇのか」
道徳の教科書みたいなうすっぺらい文句が、口からすべり落ちていく。うすっぺらいから、それは鳳にも響かなかった。
「ボクだってわかってるよ、自分が正しくないことくらい。だけど、あの子のお父さんの手術、かなり難しいものらしくって……。せめて手術が無事に終わるまでは、これ以上あの子を追い込むようなことはしたくないんだ」
「……でもっ、あんな無意味ないやがらせ、アイツ自身だって傷つくだろ」
「そうかもしれないけど……」
「それに——」
説教めいた言葉を続けようとしたけれど、もう何も出てこなかった。当然だった。これは義憤じゃないんだから。
「……楽譜」
「えっ?」
と、鳳は顔を上げた。
「あれ、おまえの楽譜だろ。汚されたりしたら、イヤじゃないのか?」
「い、イヤだよ、もちろん。でもコンクールは終わったし、楽譜はモノだから……。もし取り返しのつかないことになっても、あの子の心がそうなるよりは、まだ悲しくないよ」
そう言って、鳳は場をとりなすように見苦しく笑った。俺はその一瞬だけで燃え尽きて死にそうなほどむかついた。
「この腰抜けの偽善者!」
うすっぺらくない、ぶあつい怒りが叫びになって噴き出した。驚いた様子で力をゆるめた鳳のスキをついて、彼の手をふりほどく。大股歩きでドアへと向かう。
「日吉くん、ダメっ……!」
あわてた声が背中にぶつかる。無視してドアを開け放つ。「おい」と声をかけた瞬間、鳳の楽譜を持っていたそいつは俺を見て目をまるくした。自分の行為を咎められることへの焦り——とかではなく、「とつぜん袴姿の男に話しかけられた」ことへの困惑がありありと表れている表情だった。
「それ、おまえの楽譜じゃねえだろ」
「……あっ……」
「鳳は毎日毎日毎日、バカみたいに練習してたから入賞できたんだ。自分の努力と実力が足りてねえのを他人へのやつあたりでごまかしてるうちは、おまえは勝てねえよ!」
落選野郎は殴られたように呆然として俺を見た。さすがに言わなくてもいいことまで言ってしまった、と思って俺は焦った。
——今の言葉は、俺自身のやつあたりだ。
「……日吉くん……」
気づいたら背後に鳳が立っていた。楽譜を持っていた男はそれを俺に押しつけると、油性ペンを投げすてて逃げるように部屋を出ていった。言葉はなく、鳳も彼のあとを追ったりしようとはしなかった。
押しつけられた楽譜を開く。結局いやがらせは実行されなかったらしく、どのページも汚されてはいなかった。
「……楽譜、無事だったぞ」
背後を振り返って、鳳にそれを差し出す。次の瞬間、楽譜に向かったかと思った鳳の手は、ぺちんと音をたてて俺の手を打った。
動揺した俺の手から、楽譜が床に落ちる。鳳の手はあまりにも遠慮がちで、叩かれた、といっても痛みはまるで無かった。だけどたとえ弱い力でも、コイツが他人に手を上げたという事実に、俺は動転するほど驚いたのだった。
「……日吉くん、なんで?」
「なんでって……」
「日吉くんの言ったこと、ぜんぶ合ってるよ。正しいよ。でも」
充血して赤くなった目で、鳳は俺をにらみつけた。
「でもこれはボクの……ボクとあの子の問題だよ。たとえボクが腰抜けの偽善者でも、無関係の日吉くんが口を出していい問題じゃないだろ!」
らしくないほど強い声で怒鳴って、鳳は赤い目からまた涙を流し始めた。
——無関係。
鳳の主張が妥当なのかそうでないのか、そんなことは俺にはわからなかった。ただ、つい数分前まで俺の胸のうちを満たしていたうれしさや幸福感や、今日この会場に来てから味わったあたたかな熱のすべてが胸からあふれ出し、喉を通って涙腺へと上ってくるのがわかった。ぎりぎりのところまで押しよせてくる涙を必死で殺しながら、俺は憎い気持ちで鳳を見返した。
——泣きたいのはこっちなのに。
床から楽譜を拾い上げて、シワが寄ってしまったページの紙をのばす。『亜麻色の髪の乙女』のページが目に入ったら、ガマンがきかなくなってしまった。俺がみっともなくボロボロと涙を流し始めると、鳳は逆に泣くのをやめ、ぎょっとしたように俺を見た。
「ひ、日吉くん……」
「……」
「ごっ、ごめん、ボク言いすぎちゃって」
ぬぐってもぬぐっても止まらなくて、羽織の袖に涙のシミが広がる。鳳はまるで母親が幼い子供をなだめるみたいに、手のひらで俺の背中をさすっていた。
「……おまえ、なんで怒らなかったんだ」
「えっ?」
涙でぼやけた視界の中で、困惑した鳳の目が俺をのぞきこむ。こんなこと言いたくない、と思っても、流れ始めてしまった言葉はもう止まらなかった。
「なんで怒らなかったんだ。俺が書いてやった“おまじない”がぐちゃぐちゃに塗りつぶされても、おまえは平気だったのかよ!」
「えっ……」
一週間前の金曜日、昼休みの音楽室で、俺が書いた文字を見て「すっごくうれしい」と言った鳳の、桜みたいな笑顔を思い出す。俺もうれしかった。あのとき書いた文字のとおりに下剋上を果たした鳳を見たら、もっとうれしくなった。——なのに。
「俺の言ったこと、べつに正しくねえよ。どうするのが正しかったのかなんて知らねーよ。おまえがさかしらぶった顔で『まだ悲しくない』とか言ったのに腹が立っただけだよ。悪いか!」
“好きな人”に書いてもらうんだって言ったくせに——とは、さすがに口に出せなかった。思いのたけをぶちまけた俺の前で、鳳は俺が持っている楽譜に目を落とした。『亜麻色の髪の乙女』の、曲名の横の余白に書きつけられた俺の文字に。
背中から離れていった鳳の手が、今度は俺の右手を包み、撫でる。さっき叩いたところを癒やすみたいに。
「……ごめん」
と、神妙な声が落ちる。
「ごめんね、日吉くん。ほんとにごめん……」
「……」
「そうだよね。せっかく日吉くんが書いてくれたのに……。本当にごめんね」
ごめん、ごめんね、と謝罪が続く。続くほど、俺の心はささくれだっていく。どんなに謝られたって、楽譜を塗りつぶされそうになったときに鳳があの“おまじない”の存在を気にかけることはなかった、という事実は絶対にくつがえらないんだと分かってしまったから。
「ごめん……」
悲しさがとめどなく流れる。鉛筆書きの文字に涙が落ち、濃い線が汚くにじむ。こんなもの書かなきゃよかった、と一瞬後悔したけれど、あのとき「うれしい」と言った鳳の言葉はきっと本当だったし、鳳が金色のトロフィーを受けとったとき、俺は本当にうれしかった。
それは本当に、本当だったんだ。
***
帰り道の歩道は落ち葉で埋まっていて、一歩進むごとにガサガサと音をたてた。袴とスーツを着た子供の二人組で歩いていると、けさ一人で会場に向かっていたとき以上に衆目を集めるのがわかった。鳳は左手に鍵盤柄のトートバッグを提げ、右手で俺の手を握りながら帰路をたどった。
「……おい。手、いいかげん放せよ。おまえは俺の保護者か」
「だって今日の日吉くん、心配だから」
「心配って、それ原因はおまえだろ」
「そうだけど……」
横断歩道を渡ろうとした矢先に、信号が赤に変わる。もちろんすぐに立ち止まったけれど、鳳は不安そうな目で俺をうかがった。コイツは俺がヤケになって道路に飛び出していくとでも思っているのだろうか。
「あの、日吉くん」
「なんだ」
「……」
鳳の言葉は続かず、信号が青になり、俺たちは無言のまま横断歩道を渡った。落ち葉を踏みながら進み、いつも二人で下校するときと同じ分かれ道にたどりつく。
さっさと帰ってしまいたかった。だけど夜の色になり始めた並木道のはじっこで、鳳は物言いたげな顔をして俺の手を握り続けていた。
「おまえ、言いたいことがあるならハッキリ言えよ」
手にギュッと力を入れてやる。痛そうに眉を寄せながら、鳳はやっと口を開いた。
「……ボク、今日すっごく緊張してて。ピアノのイスに座ったとき、暗譜じゃないのに頭の中が真っ白になっちゃって、どうやって手を動かしたらいいのかわかんなくなって……」
「へえ、そうだったのか。落ちついてるように見えたけどな」
「そ、そうかな。自分では全然……でも楽譜を見て、日吉くんが書いてくれた文字が見えたら、なんか息ができるようになった、っていうか。指が軽くなって、ちゃんと動いてくれて……。だから金賞を取れたのも、日吉くんのおかげなんだよ」
「そうかよ。優しいヤツだな、おまえ」
もちろん言葉どおりの意味ではなく、皮肉として言った。それは鳳にも伝わり、鳳は傷ついたと言わんばかりの顔で俺を見た。
「ボク、フォローとかのつもりで言ってるわけじゃないよ?」
「あっそ。どっちでもいいけど、そろそろ帰らせろ」
「……日吉くん、そんなにいつまでもいじけないでよ……」
「はぁ?」
威圧する気で言い返したものの、それ以上は何も言えなかった。事実だったからだ。図星をつかれた俺の前で、鳳はなぜか頬を赤くしていた。もごもごとなにかを言いよどんでから、奇妙に熱っぽい目で俺を見る。
「……これ、ほんとはヒミツにしておこうと思ってたんだけど」
「え?」
「日吉くんに“おまじない”してもらった、きょうの前奏曲……。『亜麻色の髪の乙女』って曲名で」
「ああ、それは知ってるけど……」
前奏曲だから、それは二分くらいで終わってしまう。もっと長く聴いていたかったと思わされる、甘く心地よい旋律の曲だった。
「じゃあ、『亜麻色』ってどんな色か知ってる?」
「え、いや……考えたこと、なかったな。髪の色なんだから、黒とか茶色とかか?」
「……うん」
という短い返事のあと、鳳はようやく俺の手を放した。
「ちょっと黄土色っぽくて、灰色がかった、うすい茶色のこと」
「ふうん」
「日吉くんの髪の色、だよ」
「え」
そのとき、俺はなにかを思った。心が動き、思考する感覚が確かにあったのに、自分が何を思ったのかわからなかった。
「……だからボク、あの曲を弾くたびに日吉くんのことを思い出して。“おまじない”も、絶対あの曲のページに書いてもらいたいと思ってて」
「い、いや……でも、俺は『乙女』ではないぞ」
「うん。だけど……その曲名の由来になったのは、むかしの詩でね。亜麻色の髪をしたその人への恋のうた、だから」
「……」
——何が「だけど」で、何が「だから」なんだろう。
困惑する俺の頭に、鳳の手がふれる。髪の中に入ってきたあたたかな手が、いつくしむみたいに優しく頭皮を這っていく。なにも言えずに固まっていると、鳳はやがて俺のほうに顔を近づけてきた。
日没間際の弱い光を映した瞳が、至近距離まで迫る。えっ——と思う間もなく、ほっぺたに湿った感触が残る。一瞬で離れていった鳳は、俺の頬にくっつけたばかりの唇を指先で撫でながらうつむいた。
「……なっ、なんのつもりだよ、おまえ……」
もっと強く凄んでやろうと思ったのに、声は揺らいで動揺がバレバレになった。さっき以上に顔を真っ赤にした鳳は、「これは、そのっ」と弁解のような声をあげた。
「……おまじない! 日吉くんの機嫌が早く直りますように、って!」
「お、おまじないって……」
「じゃっ、じゃあね! また月曜日に学校で!」
「えっ、おい、ちょっと待て——」
鳳は俺の制止を聞かず、薄闇の並木道を脱兎のごとく走り去っていった。俺はその背中を追いかけるか否か迷い、結局「否」を選んだ。追いかけて追いついてみたところで、何を言えばいいのかわからなかったからだ。
立ちつくすことしかできなくなった俺の顔に、秋の風が吹きつける。まだ鳳の唾液を残すほっぺたの皮膚が、その痕跡のところだけ冷たくなる。
どくどくと心臓が鳴っていた。いっそ止まってくれと願うほどうるさかった。イヤだとか気持ち悪いとか思えれば話は早かったのに、自分のどこを探してもそんな感情は出てこないから困った。それどころかアイツの手の温度が少しずつ消えていくのが惜しい気さえして、俺は自分の髪の中に手を入れて頭を撫でたりしてしまった。亜麻色、なんてあの楽譜を見るまでは聞いたこともなかったのに、鳳があの甘やかなメロディに俺の髪を——俺を——みて演奏していたのだと知ると、自分の髪がなんだかとてもいとおしく、価値のあるもののように感じられてきた。
体が熱い。怒りとは別の作用で。いつまでもやまない動悸のせいで胸が苦しい、痛い、しめつけられるように。ほてった体が汗を出し、袴の下に着た襦袢を濡らす。自分の体なのにコントロールがきかなくて、さっきのアイツの手に感覚機能の全部を持っていかれてしまったみたいだった。
——これ、“まじない”じゃなくて、“のろい”じゃないのか?
深呼吸をしてみても、いつものような精神の統一は得られなかった。それでもどうにか平常心の断片らしきものをたぐりよせて、俺は帰り道の続きを歩き始めた。
十七時、逢魔が時の秋の街を行く。一歩進むごとに、今日あった出来事がひとつずつ脳裏に映し出される。俺の袴を指さしたガキ。鳳の演奏のあとに静まり返った会場。涙でにじんだ鉛筆書きの文字……しかし記憶は結局、さっきの一瞬のキスだけに収束し、頭には彼の姿が残る。週明けにはまた学校で顔を合わせることになる、友だちの姿が。
——月曜日にアイツに会ったら、何を言えばいいんだろう。
鳳の行動の意味なんて考えてもわからないから、俺はただ月曜日に自分が言うべき言葉だけを考えて歩くことにした。いつものように昼休みの音楽室で顔を合わせている場面を想像すると、不思議と少し落ちついた。
月曜日になったら。とりあえず、「偽善者」なんて言ってしまったことは謝ろう。それから「おめでとう」って、言いそびれていた祝福の言葉を聞かせてやってもいいかもしれない。
[23.04.07]