【説明・注意書き】
U-17合宿中、日吉くんが鳳くんから突然告白され戸惑うも、
翌日からは告白を「なかったこと」にして以前と同じように「普通の友達」として接することになり、
そのまま3か月が経過して……という話です(ハッピーエンド)。
2ページ目の冒頭からR18。
・3ページに分かれています。
・財前くんがちょっとだけ出てきます(告白の場面を目撃しちゃう役回り)。
・鳳くんのお父さん(捏造)がほんのちょっとだけ出てきます。
[R18関連]
※7.6万字のうち3.6万字くらいR18です。
※本番なし(指入れ、素股、挿入寸止めまで)。
※攻め喘ぎ、♡喘ぎ(攻・受どちらも)あり。
※受→攻の愛撫多め(フェラ、乳首責め、言葉責め等)。
※R18部分は【やや受け優位→攻め優位→受け優位→攻め優位】という感じで進みます。
ページジャンプ
・1ページ
・2ページ (R18)
・3ページ
もくじ
【1】11月 (5,000字)
【2】2月
◆2月13日 (4,000字)
◆2月14日 (11,000字)
◆2月15日 (49,000字/途中からR18)
【3】3月 (8,000字)
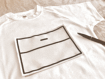
友だちの話 (1ページ)
【1】11月
深夜一時。合宿所の廊下は薄暗く静かだ。
合宿開始当初は修学旅行的なノリで夜遅くまで騒いでいる連中もいたが、みんな時間が経つにつれ夜ふかしにも飽きたらしい。ただでさえ毎日地獄のような特訓続きだから、貴重な睡眠時間を削ってバカをやるのは文字通りバカらしいというのもあるだろう。
俺自身も早寝早起きが基本だが、今日は夕食後の自主特訓に熱が入りすぎてしまった。疲労も眠気もひどく、今すぐベッドに潜り込みたいところだが、汗を流さずに寝るわけにはいかない。
「あれ、日吉……」
ふいに自分を呼ぶ声がして、俺は意外に思いながら背後を振り返った。俺と同じで、こいつが夜遅くまで起きているのは珍しい。
「鳳。珍しいな、こんな時間に」
「ん、ちょっとね。……日吉、これからお風呂?」
鳳はバスセットらしき荷物を脇に抱えて立っていた。ジャージ姿で汗もかいているから、おそらく俺と同じように自主練を終えてきたところなんだろう。
「ああ。じゃ、一緒に行くか」
「えっ」
「なんだよ。お前もこれから風呂じゃないのか?」
「……いや、そうなんだけど……」
浴場へ向かいかけた俺の横で、鳳は何事かを口ごもって固まった。戸惑うような痛がるような、奇妙に神妙な表情を浮かべながら。
「……あ、あのっ!」
「なんだ、急に大声出して」
「え、っと……俺、部屋に忘れ物しちゃったから。日吉は先に行ってて」
「はぁ?」
思わず声が裏返る。ここは211号室の——鳳の部屋の真ん前だ。
「いや、部屋ってここだろ。それくらい待っててやるよ」
「……や、でも……時間、かかるかもしれないから」
「って、何を忘れたんだ? お前」
「え、えぇと……」
鳳はふたたび言葉をなくして固まった。目を合わせると瞬時にそらされて、俺は内心で舌を打った。
「バカだろ、お前」
「え」
「ただでさえヘタな嘘なのに、よりによって付き合いの長い俺相手に通用すると思うなよ」
「……うっ、嘘じゃないし」
「そういやお前、最近なんかヘンだよな」
鳳はメンタルの強いほうじゃないし、この合宿の過酷な環境下では誰だって情緒が不安定になってもおかしくはないだろう。俺自身も自分の日々の課題をこなすことに精一杯で、他人のことにまで気を回す余裕はなかった——のだが。
「今日の午前中、保健室でたまたま宍戸さんと大石さんに会ってな」
「えっ……日吉、ケガでもしたのか?」
「いや、ちょっと深爪をして絆創膏をもらいに行っただけで……。で、そこで二人にお前のことを聞いたんだ」
「俺のこと?」
「最近なんか鳳のヤツが挙動不審ぎみだけど、部屋ではどんな感じですか、って」
レストランやコインランドリーで顔を合わせると今みたいに不可解な理由で逃げられるし、会話をしてもどこか噛み合わない。良くも悪くも繊細なヤツだから、慣れない寮生活で心労が溜まっているのだろう、くらいに考えていたが。
「二人ともピンときてない様子で、きょとんとした顔してたよ。べつにどこもヘンなところはないけどな、って」
観察力に長けた大石さんと、いうまでもなく鳳のことを誰よりもよく見て把握しているだろう宍戸さん。鳳に何か異変があれば、毎日同じ部屋で寝起きまでしているあの二人が気づかないわけがない。
——つまり。
「俺限定の挙動不審かよ、それ」
「ちっ、違う……」
鳳は俺の目を見ないまま、なおも否定してみせた。言葉のうえでは否定でも、派手につっかえた声が真実をありありと物語っていたが。
「別に日吉に対して何かあるとかじゃ……。ただちょっと……練習がハードすぎて疲れてるのかもしれないけど」
「でも部屋では普通なんだろ、お前」
「それはほら、部屋では俺だけ二年生だからさ。先輩たちの前では遠慮しちゃうだろ、どうしても」
「……」
嘘もヘタだし作り話もヘタだ。鳳のそういうニブさには慣れているはずなのに、今は無性に腹が立った。隠し事をされていることよりも、隠し事が通用する相手だと思われていることが腹立たしいのかもしれなかった。
歯切れの悪い言葉に揺らぐ声、いつまでも合わない視線。不自然としかいいようのない鳳の態度が頭に血を上らせた。——自分がどうしてここまで怒っているのか、自分でも不可解なくらいに。
「……なにか物言いがあるなら、正々堂々と跡部さんに直訴してこいよ」
「え、……は?」
「自分が部長に選ばれないからって、俺に八つ当たりなんて——」
「そんなんじゃない!」
普段めったに声を荒らげたりしない鳳の叫び声の大きさに、俺は正直ちょっとひるんだ。何も言えずにいると、どこかの部屋のドアに枕か何かがぶつけられるらしき音がした。騒音への苦情だろう。鳳はハッと我に返ったように目を見開き、さっきとは打って変わって弱々しい小声で「ごめん」と呟いた。
「でも俺、そんなこと本当に考えてない。部長としての日吉と一緒に上を目指せるの、楽しみでしょうがないくらいなのに」
「……いや、悪い。俺も決してそんなふうには思ってないが……ちょっとイラついて言いすぎた」
「う、うん……」
「でもさ」
俺は鳳の前に歩み出た。ここまで距離を詰めればさすがに逃げられないだろうと思うくらいの位置まで近づいたけれど、鳳はそれでも俺の目を見ないままだった。
「『そんなんじゃない』なら、実際はどんなんだっていうんだよ」
「……それは」
「俺の目見ろ、鳳」
俺が一歩近づけば鳳は一歩後ずさり、二歩近づけば二歩後ずさる。そんなふうにしていたら、十歩も進まないうちに鳳の背後は壁だけになった。もしも今誰かにこの場を目撃されたら、脅迫の嫌疑でもかけられそうな体勢だ。
「……日吉、近い」
「お前がさっさと白状すれば済む話だ」
先に嘘をついたのは鳳のほうなのに、こんなセリフを言ってしまったら完全に俺が悪役だ。鳳は額に汗をかき、胸の前に抱えた荷物を押し潰さんばかりの力で抱きしめながら、浅い息と一緒にかぼそい声を出した。
「俺、風呂には」
「風呂?」
「……一緒には入れない。ごめん」
「……」
なにか身体的なコンプレックスでもあるのだろうか、というのが最初に思い浮かんだ仮説だった。そうだとすれば俺は無神経な追及をしてしまったのかもしれない——と反省の念が頭をよぎったのも束の間。
「お前、この合宿に来てから普通に大浴場に入ってるよな」
宍戸さんとか樺地とか、さらには他校のヤツらとも連れ立って浴場に向かっている姿を見たことがある。要するに、これはやはり対俺限定の挙動不審だってことだ。
「……俺、お前に何かしたか」
鳳はちょっとやそっとのことで他人を拒むようなヤツじゃない。もっと我を通したっていいだろうにと、はたから見ていて歯がゆく感じることさえあるくらいに。
「俺に非があるなら、自覚がない時点でダメだろうが……。でも謝るチャンスくらいはくれないか」
「ちっ、違うよ。日吉は何も悪くなくて、ただ俺が勝手に」
「勝手に?」
ひゅっと息をのむような音のあと、鳳はようやく俺の目を見た。腹をくくったような、あるいはなにかを諦めたような目が、十センチ程度の距離からじっと俺を見下ろしていた。
「俺が勝手に……日吉のことが好き、だから」
「……は?」
「お風呂とか一緒に入ったら、絶対っ……よこしまな目で見ちゃうと思う、から……」
「…………」
鳳の瞳は悲しげに翳っていった。泣きそうな顔だなと思った瞬間、目元がぐわんとたわみ、まぶたのふちからは本当に涙が流れ始めた。
「お、おい。なんで泣くんだよ」
「ごめん……」
声は一気に水で濁り、鳳は土汚れがついたジャージの袖で涙をぬぐい始めた。広く厚い肩が縮こまり、上下に震えだした。——もしも今誰かにこの場を目撃されたら、間違いなく俺がこいつを泣かせたと思われるだろう。
——いや、実際に俺がこいつを泣かせたのか?
「ごめん。日吉。ほんとにごめん……」
「いや、その……」
「俺ほんとはこんなこと、言うつもりなくて。日吉のこと困らせたくなくて」
「……いや……」
「あのっ、……俺、もう絶対こんなこと言わないから!」
ジャージの袖の下から、真っ赤になった目もとが覗いた。涙に濡れた目はもう俺から視線を外さなかったけれど、そこにあるのは俺が見たことのない色だった。
「好きとか絶対言わないし、お風呂とか着替えとか絶対日吉と一緒にならないようにする。日吉に触ったりもしないし……明日になったら普通に、今まで通り普通に友達として接するから。さっき言ったこと、全部なかったことにするから……」
ズ、とはなをすする音がした。おびえるように震える唇から出てきたのは、細く力ない声だった。
「だからお願い。友達のままでいてほしい」
汗の玉が一粒、背筋をすべり落ちていくのがわかった。唇は動くのに空回るだけで、言葉が出てこなかった。心臓の鼓動が速いのか体温が上がっているのか、よくわからないけれど体の中がヘンだった。
——なにも言えない。けど、なにか言わなきゃいけない。
自分の前で泣いているこの友人を突き放してはいけないと、切迫した直感のようなものが俺の頭をうなずかせた。それが精一杯だった。俺の肯定を見てとってか、鳳はわずかに表情をやわらげた。
「ありがと、日吉。俺、ちょっと頭を冷やしてくる」
「……えっと、鳳」
「……なに?」
「や、その……目、洗ったほうがいいぞ。さっき汚れた袖で拭いてただろ」
「あ……」
うん、とぎこちない笑顔で呟いて、鳳は廊下を走り去っていった。
あんなに悲しそうな鳳の顔を見たのは久しぶりだった。今より小さかった頃の、幼い子供の顔が脳裏に浮かんでいた。まだ数年しか経っていないはずなのに、それはもっとずっと遠い昔の記憶のようだった。
——友達のままでいてほしい。
鳳の足音が消えて静まり返った廊下で、頭の中にさっきの言葉が響いた。なんだよそれ、と思った。思った瞬間、どこからかスマホの着信メロディらしき電子音が聞こえてきた。
「……」
音はすぐに途切れた。どこかで聞いたことのある音だった。つい最近、たしかこの合宿所の部屋の中で——
「……あ」
正解を突き止めるのと同時に、視界の端に人影が映った。反射的に身を翻すと、そこに立っていたのはルームメイトの一人だった。そういえばさっき部屋に戻ったときに財前の姿だけ見なかったな、と思い出す。
「……あー……日吉、部屋に戻るときに音立てんといてな」
片耳にイヤホンをさしたまま、財前はけだるげな一言を残して俺の脇を通りすぎた。こっちは毎日お前の音漏れも我慢してやってるのに——とか、今は言っている場合じゃない。
「おい、ちょっと待て」
「あ?」
「お前、どこから聞いてたんだ」
「……日吉が、あの……名前はおぼえてへんけど、氷帝のアイツを脅迫しとったあたりから」
「脅迫じゃない。というか、ずっと立ち聞きしてたってことか」
正直、同室のヤツらとはまだあまり打ち解けられていない。特にこの財前は部屋の中でも常に自分の世界に籠もっているような雰囲気があり、たぶん客観的にみても俺以上に取っつきにくいヤツだ。
相手の出方が読めない。みんなに言いふらされたりしたらどうしよう、もしもそうなったら鳳は間違いなく必要以上に責任を感じて自分を責めるだろう——と嫌な想像ばかりが頭をめぐる。
身構える俺の前で、財前は「はあ?」と短く声を発した。威圧的に聞こえなくもないが、抑揚が乏しいせいで凄味は感じない声だった。
「心外やわー。なんや取り込み中みたいやったから空気読んで待っててやったんやけど?」
「……お前、さっきのこと誰かに話したり……」
「はあ?」
と、財前はまた同じ言葉を繰り返した。
「あんなしょうもないネタを言いふらして回るほど、しょうもない人間と違うわ」
口ぶりがとげとげしかったせいで、意味を取るのに時間がかかった。要は誰にも言いふらしたりしないと、目の前のルームメイトは言っているのだった。
「……わ、悪い。疑うようなことを言って」
去っていく背中に声をかける。財前はこちらを一瞥すると、無言で廊下を進んでいった。
【2】2月
◆2月13日
明日は雪が降るらしい。バレンタイン当日の雪は四年ぶりだと天気予報が伝えていて、俺は四年前のその日が雪だったことを思い出した。数年前の天気なんていちいちおぼえているわけもないが、その日は雪景色の中で鳳に誕生日プレゼントを渡した記憶があったのだ。
「日吉、おはよっ!」
学校へ続く並木道の途中で、鳳は俺の名前を呼びながら駆け寄ってきた。四年前の今日も、こんなふうに朝の通学路で声をかけられたのだ。当時とも変わらないような顔をして、鳳は俺の隣を歩き始めた。
「今日も寒いな。明日は雪だってね?」
「ああ、気が滅入るな」
「俺はこの季節もわりと好きだけど……。あ、そうだ」
鳳は歩きながら鞄を探り、A4サイズの茶封筒をこちらに差し出した。受け取って中を見ると、コピー用紙の束が入っていた。
「きのう言ってた部誌サイトのデザイン、描いてきたよ。技術的なことはわからないから、細かいところの修正はおまかせするな」
「ああ……ありがとう。早くて助かる」
「今のデザインからはけっこう変えちゃったんだけど、大丈夫そう?」
薄いブルーを基調に曲線的なあしらいを多用したデザインは、寒色でまとめられているのに温かみがあって親しみやすい雰囲気だった。部誌サイトに親しみやすさが必要かどうかはわからないが、たぶん無いよりはいいんだろう。
進級まで二か月。新入生が入ってくる前に部活のサイトのリニューアルをしないかと、年末あたりに二年生の誰かが言い出した。現行のサイトはパソコンからの閲覧に最適化されていて、スマホなどのモバイル端末からだと少々使い勝手が悪いのだ。そこでモバイル対応を行うついでにシステムやセキュリティの更改も済ませてしまおうという話に発展し、休日やオフの時間を使って作業を進めているところだった。
最初は商用に販売されているテンプレートを使うつもりでいたが、既製の枠組みの応用では意外と痒いところに手が届かない。自分たちでイチから組み立ててしまったほうが早いという結論に至り、構築のベースとなるデザイン案の作成を鳳に頼んだのが昨日の放課後のことだ。
「……どのページも情報が過不足なく収められる構成になってるし、導線も直感的にとらえやすい。俺は今のデザインよりいいと思う」
「え、そうかな。そんなに深く考えて作ったわけではないけど……。使えそうならよかったよ」
鳳は謙遜めいた笑みを浮かべたが、それは素人目にも細部まで考え抜かれたデザインに見えた。感性と知性とで緻密に気を配らなければ作れないだろう。もっとも創作的な分野における鳳の技量を知っていればその出来自体に驚くことはないが、問題は完成の早さだった。
「お前、きのう寝てないだろ」
顔を覗き込んでみれば案の定、充血ぎみに赤くなった両目が見えた。一晩中パソコンの画面を見続けていたのかもしれない。
「仕事が早いのはありがたいが、そこまで無理はしなくていい。時間的にもまだ余裕があるし……」
「いやいやいや、ちゃんと寝たって! たしかにちょっと夜ふかしにはなったけど、無理したわけじゃなくて……あれこれデザインを考えてたら、つい筆が乗って楽しくなっちゃってさ」
「……まぁ、今夜はくれぐれもしっかり寝ろよ」
「うん、ありがとう」
学校に着くと、校門の周囲にはまだほとんど生徒の姿がなかった。ほの暗い早朝の空の下で、校舎はくすんだ紫のような青のようなあいまいな色をしていた。
「……日吉はこのまま朝練行くよな? 俺は花壇の水やりがあるから、ちょっと遅れて合流するよ」
「水やりって、それ生物委員の仕事じゃないのか」
「うちのクラスの生物委員の子、いまインフルエンザで休んでてさ。俺が代役やってるんだ」
「……ふうん。あいかわらずお人よしだな」
「っていうか俺、花の世話をするのもけっこう好きだし……。じゃ、またあとでな」
鳳は無邪気っぽく手を振って、花壇がある校舎裏のほうへと駆けていった。
***
「……じゃあ、サイトの特定の範囲にだけパスワード認証を設けて、一部の部員しか入れないようにすることもできるのか?」
『あぁ、そらもちろん……けど、そこまで説明すると長くなるで』
「なら、また後日教えてもらってもいいか。いつも時間を取らせて申し訳ないが」
『いや別に、こっちも暇潰しになるし。……そういえば』
「ん?」
放課後にウェブ会議アプリで俺のPC画面を共有しながら、財前にサイト構築の作業を手伝ってもらうこと早二時間。通話の音声を伝えるイヤホンの向こうで、財前は無気力げに言葉を続けた。
『このサイトの配色やらレイアウトやらって、日吉が考えたんか?』
「いや。デザインまわりは副部長の……鳳に全部任せた」
『ああ、なるほど。どうりで日吉にしては甘口すぎる思たわ』
あの合宿から三か月。知り合ったばかりの頃には想像もできなかった展開だが、同室だったメンバーとはちょくちょく連絡を取り合うようになっていた。特にIT方面に強い財前には、こうやって部誌サイトの管理について助言をもらうことが多い。PC画面を共有して俺の不慣れな操作を見せるたびに、「教えるより最初から全部俺がやったほうが百倍早いな」とぼやかれるが。
『鳳、ゆーたら……自分ら、あれからどうなったん?』
「どうなった、って」
『合宿んとき、告白みたいなこと言われてたやん。なんか進展あったんか』
「……いや、べつに何もない」
あの一件は結局、誰に知られた様子もなく今に至っていた。つまり財前は本当に誰にも口外しなかったのだ。単に興味がないだけなのだろうが、なんにせよ俺にとってはありがたいことだった。
『何もないって、じゃああれからずっと気まずいままか』
「いや、……お前も聞いてたんだろ。『全部なかったことにする』って言われた通りだよ」
今となっては夢か幻だったんじゃないかとすら思う。あの告白——もはや告白だったのかどうかもよくわからないが——のあと、一晩寝て起きたら鳳は本当に“普通の友達”に戻っていた。泣き顔で走り去っていった日の翌朝に合宿所のレストランで顔を合わせたら、あまりにも普段通りのテンションで「おはよ」と声をかけられて、その普通さに俺のほうが戸惑ったくらいだ。
誰に対しても親切で優しいように、俺に対しても親切で優しい。付き合いの長さゆえか俺の前ではときどき生意気な物言いもするが、基本的には朗らかで屈託のない、昔から変わらない一人の男友達のままだった。気まずくなるどころか、むしろ最近では部活の代替わりを経て以前よりも付き合いが密になっている。
まるで一瞬だけ異世界の夢を見せられて、すぐ現実に戻されたみたいだった。夢の中で起こった出来事について真剣に思い悩む人間なんていないから、俺もただ“現実世界”の続きを生きている。普通の友達、普通のチームメイトとして。あいつはこれでいいのだろうかと思わなくもないが、当の鳳自身が誰より普通なのだから俺のほうが態度を変えるのもヘンな話だった。
という顛末をかいつまんで話すと、イヤホンの向こうには短い沈黙が流れた。
『……ふーん。日吉も鳳もようやるな』
「どういう意味だよ」
『自分に対して下心を持ってる相手と毎日一緒におんのも、自分が下心を持ってる相手の前で友達のフリをすんのも、だいぶしんどいんとちゃうか。知らんけど』
「……下心、って」
財前の声はやはり無感情な調子で、その平板さがかえって内容に冷静な説得力を持たせているようだった。冷やかしや興味本位ではなく、客観的に事実を並べただけなのだと。
『鳳、そないなこと言うてたよな? よこしまな目で見てまうから一緒に風呂には入れへん、とか』
「……それはそうだが……。多分、あれは一時の気の迷いか何かだったんだと思う」
『きのまよい』
「あれ以来、あいつは本当に普通なんだ。こっちを意識するそぶりもないし、なにか無理をしているようにも見えない」
『……』
俺も財前も口数の多いほうではないから、普段から会話には沈黙がつきものだ。しかし今は、慣れたはずの沈黙がやけに重かった。
『いや、だからそれが演技やって話やろ』
今度は俺が沈黙する番だった。
「……お前はよく知らないだろうが、あいつはそんな器用な真似ができるヤツじゃない」
『へえ?』
「それに、下心……とかいうのも、あいつが大げさに考えてただけなんだと思う。清廉潔白を絵に描いたような人間だから」
『はあ……。たしかに優等生っぽくはあったけど、清廉潔白でも中二男子は中二男子やろ』
「……」
『正直、俺ならキツいけどな。友達や思てた相手からそういう目で見られて、毎日学校で友達ごっことか』
達観と嫌悪を混ぜたような財前の口ぶりに、自分の奥のほうで苛立ちが芽吹くのがわかった。だけど自分が何に苛立ったのかは分からなかった。苦し紛れに「お前、学校に友達なんていたのか」と茶化してみたら、イヤホンの向こうでピコンと何かの通知らしき音が鳴った。あっ、と財前の声が続く。
「なんだ?」
『観たい配信始まったからもう切るわ。んじゃ、また』
「あ、ああ……今日はどうも」
ありがとう、と言い終えるより先に通話は切れた。あいつにとっては本当にただの暇潰しだったらしい。
ノートパソコンを閉じて、文机の上に広げたデザイン画に視線を落とす。そのまま目を閉じる。——友達の「フリ」とか「ごっこ」とか、あまり聞きたくなかった言葉が暗闇の中で回り始める。
思い当たるフシがないわけではなかった。たとえば鳳のクラスの生物委員はインフルエンザで欠席などしていないのだ。彼は図書館の常連であり、俺は今日も昼休みに書架の中で顔を合わせている。
一緒に部室に行けば一緒に着替えることになる。鳳は律儀にそれを避けたんだろう。
べつに着替えくらい一緒でも俺は気にしないのに、と思う。だけどなんとなくその言葉を伝えることができないまま、三か月の月日が経っていた。
***
◆2月14日
予報の通りバレンタイン当日は雪になり、テニス部も室内での練習を余儀なくされた。トレーニングルームでの練習を終えて部室に戻ると、ダッフルコート姿の鳳がパソコンに向かっているところだった。鳳は部屋に入った俺に気づき、「おつかれさま」と相好を崩した。
「おつかれ。今日の部誌当番、お前だったか」
「ああ。いま書き終わったところだよ」
「あ……そうだ、せっかくだから見てもらおう」
「うん?」
隣の席に掛けて、横からパソコンを操作する。構築中の新しい部誌サイトを表示させると、鳳は「わっ」と感嘆の声をあげた。
「すごい、俺の描いたデザインがそのままサイトになってる……」
「まだ全然作りかけだけどな。これ、どこか直したほうがいいところはないか? デザイナーの意見を聞きたい」
「デザイナーって、そんなたいそうなものじゃないけど……。細かいところまで忠実に再現してくれてるし、文句なしだよ。日吉、こんなこともできるんだな」
もちろん俺だけの力でそこまでのクオリティを実現できるわけもない。財前の助けを借りたことを伝えると、鳳は「なるほど」と呟いた。
「しいていえば、ってレベルのことでもいいんだが。なにかあるなら早いうちに修正しておいたほうが後々ラクだしな」
「うーん……そうだな。じゃあ、このアクセントに使ってる茶色だけど」
鳳の指先が画面に近づき、サイトヘッダー下部の罫線を指す。見出しの文字や箇条書きのビュレットに使っているのと同じ色、濃いブラウンの罫線だ。
「これ、もう少しだけ青みがあるといいかも」
「青み?」
「ちょっと貸して」
マウスを渡すと鳳はペイントソフトを開き、やがてそのキャンバスを深い茶色で塗りつぶした。
「この色のほうがメインの水色にもなじむし、全体が締まるかなって……俺は思ったんだけど、どうかな?」
「ふうん……」
ペイントソフトとブラウザを見比べる。二種類の茶色に微差があることは一応見て取れたが、新しい茶色をデザインに落とし込んだときの仕上がりまではイメージできなかった。
「……正直俺にはピンとこねーけど、お前が言うならこっちのほうがいいんだろう。直しておくよ」
「いや、そんな。日吉が見て今の色のほうがいいと思ったら、今のままで全然いいからな」
「ん」
俺はカラーコードをメモしてパソコンを閉じ、立ち上がってロッカーの前に移動した。窓の外は薄暗く、下校時刻が迫ってきていた。さっさと着替えて引き上げなければならない。
ジャージのファスナーを下げて腕を抜いた——瞬間、背後から声がかかった。
「日吉、あとはもう帰るだけだよね。俺は職員室に用があるから、校門のところで待ち合わせしようよ」
「……ああ」
「俺はたぶん五分くらいで済むけど、日吉はゆっくりでいいからな」
「……」
鳳は立ち上がって両手に荷物を提げ、ドアのほうへ歩いていった。
「鳳」
「なに?」
「……お前、本当は職員室に用事なんてないだろ」
「へっ」
という間抜けな反応のあと、鳳は鞄から糸綴じの冊子を取り出した。黒い布張りの表紙のラベルには、〈2年C組 学級日誌〉と油性ペンの文字が書かれていた。
「用事、ほんとにあるよ? 俺きょう日直だったんだけどさ、日誌を提出するのを忘れてて。先生に渡しに行かなきゃいけないから」
「……」
「日吉、へんなの。じゃ、またあとでな」
ドアが開き、鳳の姿が消える。遠慮がちに閉められたドアの向こう側で、やけに速い足音が逃げるように遠ざかっていく。
***
一人で着替えて部室の照明を落とし、外に出た。空はもう夜の色で、雪はいつのまにかやんでいた。
五分で終わると言ったのに、鳳は俺より遅れて校門にやってきた。「先生に呼び止められて話し込んじゃって」と頭を下げた鳳の両手には、大量のプレゼントを収めた大きな紙袋がひとつずつ提げられていた。
「すげー量だな、今年も」
「うん……みんな気を使ってくれてるんだろうね。バレンタインのうえに誕生日なのに何もなかったらさすがにかわいそうだし、って感じで」
「……そういうことではないと思うが」
特段謙遜でもなく言葉通りに考えているんだから嫌味なヤツだ。普通に人望の証だし、普通に人気の証だろうに。
「片方持ってやるよ、それ」
「えっ、大丈夫だよ。大きいけど重くはないし」
「べつに親切で言ってるわけじゃない」
「え?」
俺は鳳の右手から紙袋を奪い取り、コンクリートの地面を顎で指した。歩道も車道も雪で濡れ、ところどころで路面凍結が起こっていた。
「両手どっちも塞がってたら、万が一すべって転んだときに危ないだろ。それで面倒をかけられたらこっちが迷惑なんだよ。前にもあったしな、そんなこと」
「ああ……」
鳳の視線が地面に落ち、それから俺の手元に移動する。帰路を進み始めた俺の隣で、鳳は「ありがとう」と笑った。
「やっぱり優しいな、日吉」
「だから、べつに親切で言ってるわけじゃない」
「とげとげしいのは言葉だけだよね。言ってることは優しいよ」
「……」
「——そういえば、これ日吉に話そうと思ってたんだけど。今日の昼休みにさ……」
暗く寒い帰り道で、会話は何の滞りもなく続いた。鳳がたわいない雑談を振り、俺はそれに対して一言二言返す。何年も前から変わらない、いつも通りの応酬のパターンだ。
だけど今、俺の内心はいつもとは違っていた。平穏に普通に時間が進むほど、見たくない言葉が目の裏に見える。聞きたくない声が耳の奥で聞こえる。——友達ごっこ、と言った財前の声が。
——こいつ、なんでこんなに普通なんだよ。
横目でうかがってみても、鳳の表情はいたって爽やかだ。一点の曇りもない。これが“ごっこ”すなわち演技なのだとしたら見事だが、限りなく馬鹿正直なこいつにそんな芸当ができるだろうか。あのときの告白(?)はやっぱり何かの気の迷いで——あるいは夢か幻で——俺のことが好きだとか、今の鳳は微塵も思っていないんじゃないだろうか。——あのときの言葉のように全部なかったことに“した”のではなく、本当に全部なかったことに“なった”のだ。
「……日吉、疲れてる?」
「え?」
「さっきから顔色がよくないよ。俺なんかよりよっぽど無理してるんじゃないか?」
「……」
——全部お前のせいだろ。
腹の奥から湧き上がってきた気持ちは一気に喉元まで上がり、しかしギリギリのところで噛み殺されて体の底に落ちた。落ちて、そのまま周囲を焼き始めた。火は強く、なぜか怒りとは違う未知の熱さを持っていた。
俺たちはすでに学校の前から続く大通りを離れ、ひとけの少ない一方通行の道路を歩いていた。あと数分も行けば、いつも鳳と別れる十字路に着いてしまう。
「……おい」
立ち止まって呼びかけると鳳も足を止め、こちらを振り返った。鳳の背後には、すでに明かりの消えた古い喫茶店のショーケースが見えていた。
「どうしたの?」
「話がある」
鳳の瞳の表面がかすかに揺らいだ。しかしその内心は読み取れないままだ。
——本心が知りたい。こいつが何を考えているのかわからないせいで、いつのまにか俺のほうが普通の友達としてふるまえなくなっている。
「鳳、お前——」
俺のことを本当に友達だと思っているのか——と聞くつもりだった。だけど一瞬早く、「危ない!」と叫んだ鳳の声が俺の声を止めた。
コートの上から腕をつかまれ、グイと痛いほど引っぱられる。そのまま体ごと鳳の腕の中に確保された瞬間、ものすごい風圧と轟音が背後に近づき、そして遠ざかった。凍結した道でスリップを起こした車が通りすぎていったのだ、と遅れて理解する。
「……」
速い呼吸の音がしていた。自分のものなのか鳳のものなのかわからなかった。俺の身を抱きとめている腕の力は驚くほど強く、ぎゅっと体を締められる苦しさのせいで心臓が乱暴に打っていた。
「……日吉、だいじょうぶ?」
おびえきってかすれた声が、切れ切れの吐息と一緒に耳にかかった。あたたかい吐息が冷たい耳をくすぐり、心臓はまたドクンと高鳴った。背筋に寒気が走った。足元に目を落とすと、リボンのついた小箱がいくつか転がっているのが見えた。俺を助けようとしたときに鳳が紙袋を手放し、中身があたりに散乱したのだろう。
「日吉?」
「……」
なにか答えようと思っても口からは呼気しか出てこなかった。声の出口を縛って留められてしまったみたいに。
おそるおそる顔を上げたら、至近距離からこちらを見下ろしている鳳と目が合った。目の表面はうっすらと潤み、涙ぐんだまま一心に俺を見つめていた。まなざしは熱を持っていて、暗がりの中でもはっきりとわかるくらいに頬が赤かった。
「……放せよ、気持ち悪い!」
ぶかっこうに裏返った声の、ひどくぎこちない叫びが耳に入る。これは誰の声だ、と思った。それくらい現実感がなかった。
自分が発してしまった言葉の非道さを悟るより早く、支えを失った体が地面に落ちた。俺はプレゼントの紙袋の横に尻餅をつき、腰から背にかけて鈍い痛みが貫いた。でもそんなことは今どうでもよかった。また泣かせてしまったんじゃないかと思いながら目を上げたけれど、想像に反して鳳は冷静な顔をしていた。
「……ごめん。痛かったよね」
「いや、お前は何も——」
放せと言ったのは俺だ。言われた通りにしただけの鳳に非はない。
「ごめん」
謝らなきゃいけないのは俺のほうなのに、耳にはまた詫びの言葉が落ちてきた。地面に散らばったプレゼントや紙袋を拾おうともしないまま、鳳は眉を寄せた。痛みに耐えるようなしぐさだった。
「約束、破っちゃった」
「約束って……」
「日吉のこと触ったりしないって言ったのに、俺」
「違う。さっきのは気が動転して、ただ……」
「ごめんね」
鳳はもう俺の言葉を聞く余裕もないみたいだった。冷静に見えていた表情はみるみるうちにゆがみ、口調は切迫していった。
「日吉が車にひかれちゃうって思って、ただ助けようとしたんだけど。でも日吉に触ったときに俺、なんかどうしても幸せな気分になっちゃったから……。結局、同じことだよな」
「……いや、助けてくれて感謝してる、本当に。謝るのは俺のほうで——」
「ごめん」
もう何度目の謝罪だろう。しかしそれは謝罪ではなく、俺の言葉の続きを潰すための重石だった。
「ごめんね、ずっと友達のフリしてて。日吉に無理させるの、もうやめるね」
「やめるって……」
あと一回まばたきでもすれば泣き出しそうだった。だけど鳳はまばたきをするよりも早く、俺に背を向けて走り去っていった。
「おい、走ったら危ない……」
すべって転ぶんじゃないかという俺の不安をよそに、鳳は一目散に帰路を駆けていった。ラケットバッグを背負った背中が一歩ごとに小さくなり、やがて曲がり角の向こうへ消えた。
俺の周囲にはプレゼントの箱が散らばったままだった。俺はそれらを回収して紙袋に収め、立ち上がった。地面に打った腰が痛かった。しかしその痛みも遠く、なにか他人事のようだった。——それよりも、火が。
さっき生まれた火が勢いよく燃え上がり、ふたたび体の中を焼いていた。
俺の体を抱きとめていた腕の力の強さ。自分が鳳にぶつけてしまった言葉。あからさまに傷ついた顔で詫び言を重ね、逃げるように去っていった後ろ姿……この数分のあいだに起こった出来事がかわるがわる脳裏に映った。状況はこじれていて、泥沼に近かった。俺を見下ろしながら顔をゆがめていった鳳の表情を思い出すと、心臓に針を刺されるような痛みを感じた。あいつのことを傷つけたのは自分なのに、まるで俺自身が傷つけられたみたいに。
それなのにこの火は心地よかった。
***
二月十四日には白と赤の色がついている。日の丸でも赤十字でもなく、体操服に広がった血の色だ。
四年前のその日、俺はおろしたばかりの新しい体操服を持って学校に向かった。サイズが合わなくなり、進級を待たずして買い替えることになったのだ。
サイズが変わったということは体が大きくなったということ。小学四年生だった俺は自分の体の成長が誇らしく、新しい体操服を着るのも楽しみだった。まだ学校で家庭科の授業は始まっていなかったけれど、親から針と糸を借りて名札の縫い付けも自分でやった。
いつもより少し早起きして家を出ると、外では粉雪が舞っていた。傘をさすほどではないと思ったが親に持たされた。雪は次第に強くなり、やっぱり傘があってよかったと思い始めた頃に背後から声をかけられた。
「日吉くん、おはよっ!」
「……おはよう」
通学路の途中で駆け寄ってきた鳳はコートも着ず、半ズボンの下にはむきだしのひざこぞうが覗いていた。かろうじて手袋はつけていたが、コートや防寒具はもちろんタイツの上に厚手の靴下まで重ねていた俺はその姿を見るだけで身震いがした。
「きょうは寒いね~。雪なんてひさしぶり」
「いや、寒いならコートぐらい着てこいよ」
「うーん……でも動いてたらあったかくなるし、コートまでは必要ないかなって」
「……傘、入るか?」
「えっ、いいの?」
鳳はニコニコとうれしそうな笑顔で傘の中に入ってきた。
「ありがとう。それじゃ、傘はボクが持つよ」
「ああ」
「日吉くん、きょう全身モコモコでかわいいね?」
鳳は俺の顔から足元までを見やって言った。真冬の冷たい空気の中で、視線が通っていったところだけ少し暖まったような気がした。
「おまえ、男が男にかわいいとか言うなよ。うれしくねーし」
「え~……でもほんとにかわいいんだもん。それに日吉くんは男の子も女の子も関係なく言わないよね、そういうこと」
「……」
「そういえば、きのうピアノの練習で先生がね……」
鳳の雑談にうなずいたり相槌を打ったりしているうちに、周囲には少しずつ氷帝へ向かう通学生が増えてきた。ちらほらと顔見知りの姿も見え始め、俺はためらいながらも足を止めた。
「日吉くん、どうしたの?」
「……その……」
俺はランドセルの中からラッピングバッグを取り出し、鳳の前に突き出した。鳳はぽかんと口をあけて俺を見返した。
「……なに驚いてるんだよ。おまえ、きょう誕生日なんだろ」
「えっ……うん、そうだけど。でもまさか日吉くんが……」
「べっ、べつにただの義理だし。たいしたモンでもねーからな」
本当にたいしたものではなかった。百貨店の上のほうの階にある文房具店で買った、全国どこにでも売っている国内大手メーカーの缶ケース入り色鉛筆セット。十二色入りか二十四色入りかで小一時間迷ったすえに後者を選んだため、まだ十歳の小学生にとっては小さくない出費になったものの、わざわざ誕生日プレゼントとして選ぶにふさわしい品ではなかったと思う——が。
「あ、ありがとう……」
傘の中に電灯でもついたのかと思うくらい表情を輝かせて鳳は喜んだ。傘がなければそのまま抱きついてきそうな勢いで。
「ほんとにありがとう、日吉くん! ボク絶対ぜったい大切にする!」
「いや実用品だから。適当に使ってくれ」
「じゃあ、すっごく大事に使うね」
鳳はガラス細工でも扱うような丁重さでプレゼントをランドセルに収め、きらきらした顔のまま歩き始めた。上機嫌によってどんどん速くなる歩調についていくのがしんどいくらいだった。——学校のそばにある橋の手前にさしかかるまでは。
「あっ……」
橋のたもとで、鳳は小さな声を上げて立ち止まった。橋のほうを向いたその視線を追ってみると、赤い欄干に立て掛けられた自転車と、その脇で床板に散らばった大量の荷物を拾い集めている男の姿が目に入った。そばには浅型のワイヤーバスケットも転がっていたから、おそらく自転車の荷台に固定していたそれが何かの拍子に——雪に濡れた橋の上でタイヤがスリップしたのかもしれない——外れて落下し、中身の荷物をぶちまけてしまったんだろう。
「日吉くん、ちょっと傘持ってて」
「え」
鳳は俺に傘を持たせると、橋の中を迷いなく駆けていった。俺もその背中を追い、橋の上に点々と落ちた荷物を拾い集める鳳の頭上に傘を掲げて歩いた。
赤い手袋をつけた鳳の手が革製の財布を拾い上げたときだった。その男が突然こちらを振り返り、鳳を怒鳴りつけたのだ。正確な言い回しは覚えていないが、この泥棒——みたいなことを。
「えっ……」
後ろ姿を見ているだけでも、鳳の顔がショックでひきつっただろうことが手にとるようにわかった。鳳は手に持っていた荷物を取り落とし、それから蚊の鳴くような小声で「ごめんなさい」と呟いた。——謝る必要なんてなかったのに。
男は多分、本気で鳳のことを泥棒だとか思ったわけではなかったんだろう。ひとけのない路地裏や夕方の薄暗い時間帯ならともかく、衆人環視の朝の通学路のどまんなかで、通っている学校が一目瞭然の服装で、しかも友人と連れ立って小学生が大人から盗みを働くなんて普通は考えない。
理由は知るよしもないが、きっと虫の居所でも悪かったのだ。荷物を落として不機嫌が悪化したタイミングで目の前に現れたおとなしそうな小学生が、彼にとって八つ当たりの手段としてあまりにも“手頃”だった、というだけなのだと思う。鳳も当時は年齢相応に体が小さかったし、いかにも無害そうな見てくれだったから、大人の目からは特に御しやすそうな子供に見えただろう。
「……あの、ボク荷物を渡そうと思って……」
声はかすれて震えていた。拾い直した荷物を持った鳳の手から、その男は荷物をふんだくるように奪い取っていった。チッ、とわざとらしい舌打ちの音をたてながら。
——くだらねー大人。
俺の頭には怒りよりも呆れの感情が先に来た。人間は上を見て生きるべきだ。自分より立場の弱い相手をストレスのはけ口に利用するなんて、なにより唾棄すべき行為だろう。
「……ただの善意だってわかってるくせに。おとなげない野郎だな」
俺はつい口を出していた。小学生に歯向かわれるのは想定外だったのか、男は虚をつかれたように静止した。
「鳳。行くぞ」
「え……」
俺はきびすを返し、鳳の手を引っぱって歩道に戻った。正直なところ、報復でもされやしないだろうかと少しビビってもいた。しかし橋のたもとまで進んだところで背後をうかがうと、男の姿はすでに橋の上から消えていた。
「ったく……あんなヤツ相手に下手に出てやる必要ないんだぞ、おまえも」
鳳は青ざめた顔をして黙り込み、ただ俺の手を握りしめていた。俺はその手を振りほどくこともできず、鳳から遠いほうの手で傘をさして歩いた。数分前までの上機嫌が嘘のように、鳳はとぼとぼと遅い歩みで俺の横をついてきた。
「……おい、あんまり気にするなよ。さっきのヤツ、本当におまえに財布を盗られると思ったわけじゃなくて、ただ気が立ってただけだって」
「わかってるよ」
「え?」
「本当に泥棒だと勘違いされて怒られたなら、そっちのほうがまだずっとよかった……」
冷静な口調が痛々しかった。鳳はますます表情を暗くした。俺はその表情を見て困り、とっさに目をそらしていた。なぜか無性に見ているのがつらかった。歩きながら一瞬だけ目を閉じると、まぶたの裏に鳳の笑顔が見えた。いつも俺の前で見せている、なんの屈託もなく綺麗な笑顔が。
鳳の足つきは力なく不安定だった。俺が車道側を歩いていてよかったと密かに安堵したが、鳳はやがて「わっ」と声をあげて派手に転倒した。割れたまま補修されていなかった側溝のフタに足をとられてしまったのだ。
「痛っ……」
それはほんの十数センチ程度のすきまだったけれど、子供の細い脚を捕らえるには十分な幅だった。右足だけが側溝の中に落ち、鳳は前のめりに転んで地面に膝をついた。左の膝から脛にかけて、コンクリートに擦れた皮膚からは血が噴き出した。俺は鳳の脇にしゃがみこんでハンカチで血をぬぐったが、薄いハンカチ一枚程度ではどうにもならない出血量だった。
「ごっ、ごめん、日吉くん」
「おまえ、絆創膏とか持ってねーよな」
「うん、持ってない……」
血は止まる様子もなく、裂けた皮膚を伝い落ちて地面まで赤く染めていた。どうにかしなければと焦ったとき、ランドセルの脇の金具に提げた体操服袋が腿にぶつかった。
「……おまえのクラス、きょう図工の授業あったよな?」
「えっ」
「ハサミとかテープとか、持ってないか」
「セロハンテープは持ってるけど、ハサミは教室に……カッターならランドセルに入ってるけど」
「ああ、カッターでもいいか」
鳳のランドセルを開けると、カッターとセロハンテープの他にカッターマットも入っていた。カッターマットを地面に置き、その上で体操服のシャツを細長い帯状に切っていくと、輪っかになった白い生地は厚みも伸縮性も即席の包帯にうってつけの具合だった。
「日吉くん、それ体操服……!」
「いいからさっさと脚に巻け。無理そうだったら俺がやるけど」
「……」
「おい、聞いてるのか?」
鳳は我に返ったように顔を上げ、“包帯”を手に取って左脚に巻き始めた。巻き終わった包帯をセロハンテープで固定すると、ひとまずその場しのぎの止血はできたように見えた。
「あくまでも応急処置だから、早めに保健室に行かないとな。立てるか?」
「……う、うん」
鳳は俺の片手につかまって立ち上がり、側溝から右足を抜いて歩き始めた。一歩進むたびにしかめられる表情が激痛を物語っていた。〈4-A 日吉〉の名札がついた体操服の包帯にはあっというまに血が滲み、赤い染みはどんどん大きくなっていった。
「……日吉くん。この体操服、新品だよね?」
「ああ……そういえばそうだったかな」
「本当にごめん、ボクのせいで。新品じゃなくても申し訳ないけど、よりによってこんな……。新しいの、買って返すね」
「いや、べつにいいよ。もう一枚予備のがあるし」
本当は予備なんてなかった。学校に着くと鳳は保健室で手当てを受け、俺は学校の備品の体操服を借りて体育の授業に出た。一日の授業を終えて家に帰ると、居間には俺の好物やら普段はめったに食べさせてもらえない高級菓子やらが並んでいた。学校からの連絡で一連の顛末を知った親が“ごほうび”として用意してくれたものらしかった。
老舗菓子屋の和三盆は極上だった。舌の上で溶けるその美味を味わっていると家の呼び鈴が鳴り、家事で手が離せなかった親のかわりに俺が玄関に出た。鳳が親と一緒にあいさつに来るとは聞いていたが、戸を開けた先に立っていたのが彼の母親ではなく父親だったので俺は一瞬うろたえた。あとから鳳に聞いたところ、あの日はたまたま仕事が早く終わって帰宅していたらしい。
鳳の父親はスーツ姿で、いかにも格式の高そうな、地位のある大人の男の空気をまとっていた。彼は十歳の俺に向かって深々と頭を下げ、怒涛のような感謝と称賛と菓子折りと新品の体操服をよこした。しじゅう感激したような笑顔で「いつも長太郎が話している通り本当に優しくて勇敢な子だね」とか「礼儀正しいしお行儀もいいし所作も綺麗だし」とか「学校では文武両道で優秀なんだってね」とか返事をするスキもなく矢継ぎ早に褒め倒されると、俺はだんだん頭がくらくらしてきた。やがて彼が鳳に「先に車に戻ってるな」と声をかけ、やはり丁重な一礼とともに去っていったあと、鳳はまず「日吉くん、顔がまっかになってる」と冷やかしてきたくらいだ。
「うっ、うるせえ。なってねーよ」
「なってるよ?」
「……つーかおまえ、車で来たんだな」
私服の半ズボンをはいた鳳は、すりむいた左脚だけでなく右の足首にも包帯を巻いていた。おそらく側溝に落ちたときにひねっていたんだろう。
「歩くのもキツいのか、それ」
「あっ……そうじゃなくて。念のためにお医者さんで見てもらおうって、お父さんに車で連れていってもらうことになったんだ」
「ああ、なるほど」
「……日吉くん、本当にありがとうね」
五年分くらいの感謝の言葉を一気に浴びせられて食傷さえしていた俺の前で、鳳はなおも頭を下げた。
「ケガの手当てのこともそうだけど、その前にボクをかばってくれたのも。ボク、ちゃんとお礼できてなかった」
「べつに。親切でやったわけじゃねーし」
「え?」
「いい歳して幼稚な大人に腹が立っただけだ。お前をかばったとかじゃない」
鳳はきょとんとした表情で沈黙してから、腹が立つほど幸福そうにほほえんだ。
「そっか。じゃあそういうことにしておくね」
「……」
「そっちは親切じゃない、ってことにするけど……。でも、いつも助けてくれてありがとう。ボク、日吉くんみたいに強くなりたいな」
「……いや、俺はべつにそんなに強くねーよ」
「そんなことない」
と、鳳は語気を強くした。
「日吉くんは強いよ。ボクだったら絶対、あんなふうにはできない」
「あんなふうに、って」
「ボクあの人に怒鳴られたとき、ショックで頭の中が真っ白になっちゃって。自分が悪いわけじゃないことはわかってたのに……っていうか、わかってたからこそ怖くて。うまくいえないんだけど……」
「……ま、おまえはそういうヤツだよな」
「え……」
「おまえは人の悪意に慣れてないし、慣れる気もないだろ」
「悪意」
俺だって別に世間の闇とかを知っているわけじゃない。むしろ鳳と同じように、基本的には優しい人たちに囲まれて、恵まれた環境で幸福に育ってきたほうだ。それでも子供なりに、優しくないものに対する多少の耐性は持っていたと思う。
「正直俺にはよくわかんねー感覚だけど、でも……」
「でも?」
「それって弱いわけではないんじゃないか。って、けさのおまえを見てて思った」
人の善意を信じて疑わない。だから綺麗じゃない感情に慣れていない。そしてたぶん綺麗なものばかりではないだろう世界の中で、人の悪意にさらされて鮮やかなまでに傷ついていた鳳の純粋さも、それはそれでひとつの強さであるような気がした。
「だから、おまえは俺みたいになる必要もないし……っていうか、なれるわけもないしな。それがおまえなんだから」
と言ってから、最後に付け加えたひとことの恥ずかしさに気づいて顔が熱くなった。しかし鳳は茶化すでもなく、「でも」と続けた。
「あんなふうに日吉くんにかばってもらって、守ってもらうばかりじゃ申し訳ないよ」
「だから、おまえをかばったわけじゃねえよ」
「あ……えっと、それはあくまでもたとえ話で」
「それに、『ばかり』ってわけでもないだろ。俺のほうが助けられることもあるんだから、おたがいさまだし。おまえにできないことが俺にはできるなら、べつに今のままでも困ることはないんじゃないか?」
「えっ……」
息をのむような間のあと、鳳は俺から目をそらした。普段のあいつらしくない、どこか煮え切らない視線の泳がせ方だった。
「……そ、そっか。そうなのかな?」
「なんだよ。俺、なんかヘンなこと言ったか?」
「ううん、ヘンってわけじゃないけど……」
鳳はそこで言葉を切り、足元の包帯を見下ろした。
「……日吉くんが作ってくれた包帯をほどくとき、ちょっとさみしかったな」
「え、……なんでだよ」
「うーん、なんでだろう。……じゃあ、またあした学校でね。きょうは本当にありがとう」
鳳は質問の答えをはぐらかしたまま去っていった。歩き方は不自然だった。やはり相当の痛みがあったんだろう。
——照れ隠しでもなんでもなく、あの男にたてついたときの俺は鳳をかばったわけではなかった。自分よりずっと年長の人間の精神の未熟さをまのあたりにして落胆し、その失望感によるいらだちがあの一言を言わせただけだったのだ。
だけどもし次にまた同じような状況に置かれたら、俺はまずあいつのために怒ってしまうんじゃないだろうか。
雪景色の中で小さくなっていく鳳の背中を見送りながら、俺はそう思った。自分の中のどこから生まれてきたのかわからない感情だった。
***
◆2月15日
休日でも五時起床。小学生の頃から変わらない俺の生活習慣だ。それより遅くても、早すぎてもいけない。毎日の生活リズムを一定に保たなければ心身の均衡も保てない。
しかし今日は二時間も早く、三時過ぎに目がさめてしまった。布団に入り直しても寝つきが悪く、二度寝もできないまま一時間が経過した。諦めて布団から出、文机の上のライトをつけると、襖の脇に置かれた二つの紙袋が異様な存在感をもって暗がりに浮かび上がった。
きのう鳳は結局バレンタインのプレゼントを全部道端に落としたまま走り去っていったので、しかたなく俺が持ち帰るはめになったのだ。おかげで帰宅した際、玄関先で居合わせた兄に「お前いつからそんなにモテるようになったんだ!」とか騒がれてウザかったが無視した。事の経緯など、相手が家族でなくとも説明できるたぐいのものではなかった。
真冬の早朝の空はまだ夜の色をしている。定刻通りに道場へ行き、朝稽古をこなして戻り、朝食を食べ終えたところでようやく家の中に朝の光がさしてきた。
今日は部活もない。隣町の図書館まで出向くつもりだったが、予定は変更せざるをえない。俺は自室で部誌サイトの作業を進め、九時過ぎに切り上げてスマホを取った。
鳳に電話をかける。短い電子音のあと、「電源が入っていないか、電波が届かない場所に……」のアナウンスが返る。数分おきに試してみても状況は変わらず、メールやメッセージアプリで呼びかけても反応はなかった。家の電話にかければ取りついでもらえるかと思ったが、こちらも留守電に終わった。
「……」
もし外出中ならスマホの電源は切らないだろう。家が留守電ということは家族は不在だろうが、鳳自身はおそらく在宅している。固定電話の着信音を聞いて受話器を取りかけたが、ナンバーディスプレイ機能で表示された俺の番号を見てその手をひっこめた——というのが、もっとも現実的な説であるように思われた。
アポなしで家を訪ねるなんて無礼な真似は避けたかったが、今は他にどうしようもない。俺は身支度を整え、例の紙袋を持って鳳の家に向かった。逃げるにしても自分の荷物くらいは持って帰れよと昨日は思ったが、この荷物を届けるという口実のあることが今はありがたかった。
道には夜のうちに降った雪が積もっていて、スニーカーの中には次第に冷たい水がしみてきた。長靴で来ればよかったと後悔した俺の思考を嗤うみたいに雨まで降ってきて、鳳の家に着く頃には自分も荷物もずぶ濡れになっていた。
チャイムを押すと意外なほど早くドアが開き、寝巻きみたいな格好の鳳が姿を見せた。居留守でも使われるかと思っていたが、濡れ鼠になった俺の姿をインターホン越しに見て慌てたのかもしれない。
「日吉……どうしたんだよ、そんな格好で」
「いや、これはただ傘を忘れただけで」
とりあえず入って、と促されて玄関に上がる。鳳は駆け足で廊下の奥に消え、タオルを持って戻ってきた。俺は手渡されたタオルで頭を拭きながら、足元に置いた紙袋に目を落とした。
「お前、昨日これ置いてっただろ」
「……わざわざ届けにきてくれたのか?」
「ああ。けど雨に降られて、中身が無事かどうかはわからない。悪い」
「そんな、勝手に置いて帰った俺が悪いんだし」
「いや、それは別に……」
「……」
やはり家族は不在なのか、家の中は静かで物音ひとつ聞こえない。会話の間にできる沈黙が耳に痛かった。
「……とりあえず、お風呂入ってきなよ。今はちょうど家族もみんな出かけてるし」
「え、でも……」
ためらった俺の前で、鳳は眉根を痙攣させた。目はひどく充血していた。
「べつに何もしないよ」
「あ……いや、違う、そんな意味で言ったわけじゃない。突然押しかけたうえにそこまで世話になるのは申し訳ないと思っただけで」
動揺で声が揺らいだ。まごうかたなき本心なのに、こんなふうに言ったらまるで弁解みたいだ。
鳳は俺の言葉を無視して続けた。
「風呂場の場所、わかるよな? あとでドアの前に着替えとか置きに行くから、先に入ってて。洗濯機も使っていいし」
「ああ……悪い、何から何まで」
鳳は紙袋を持ち上げ、ドアを施錠すると無言で立ち去った。俺は濡れたスニーカーと靴下を脱ぎ、浸水を免れていたポケットティッシュで足を拭いてから風呂場に向かった。
風呂で体を温めて出ると、ドアの前にはバスタオルと着替えと未開封のパッケージに入った下着が用意されていた。着替えの洋服は一年生の秋ごろに鳳が着ていたものだった。当時の鳳の背丈は今の俺より少し高いくらいだったな、と思い出す。
俺は着替えて二階に上がり、鳳の部屋のドアをノックした。ドアはすぐに開き、普段着姿になった鳳が顔を覗かせた。
鳳が用意してくれた着替えは淡いライムグリーンのケーブル編みセーターに生成り色のデニムパンツという組み合わせで、自分でもヒくほど俺には似合っていなかった。普段の鳳だったら意気揚々とからかってくるんだろうな、と思う程度には。
「髪、濡れたままで大丈夫?」
「……ああ、ほっとけば乾くし」
——しかし今はそんな軽口もない。鳳は俺の顔を見ず、「そこ座っていいよ」と床のクッションを指すだけだった。背の低いガラステーブルの上には、まだ湯気のある紅茶が用意されていた。
「紙袋の中身、ちゃんと無事だったよ。わざわざ届けてくれてありがとな」
「ああ、それならよかった……」
「でも日吉、荷物を届けにきたわけじゃないよね」
鳳は静かに言った。俺は無言で頷いてクッションに腰を下ろした。テーブルの向かい側に座った鳳は、紅茶を少し飲んでから口を開いた。カップの持ち手にふれた指先が震えていた。
「日吉は優しいから……気持ち悪い、って言ったことを謝りにきてくれたんだろ。でも」
「でも?」
「もう俺にとってはどっちでもいいし、どうでもいい」
「……どういう意味だ」
「だって謝られても謝られなくても、なにも変わらないから」
声は語尾にかけて細り、最後には涙と混ざった。
「お、おい……泣くなよ」
「うるさいな。好きにさせてよ……」
「……なにも変わらないって、何が変わらないんだ」
鳳はしばらくシャツの袖で目元を押さえていた。声も上げずに泣き続ける友人の姿を見ていると胸が痛んだ。四年前と同じように一瞬だけ目を閉じてみたけれど、今は幻ですら彼の笑顔を見ることはできなかった。
ぐしゃぐしゃに濡れた顔が俺を向く。目が合った一瞬だけで、俺は心が粉々にすり減ったような気がした。
「日吉が謝っても謝らなくても、日吉にとって俺が気持ち悪い相手なのは変わらない。もう日吉と友達でいられないってことも変わらない。だからどっちでもいいし、どうでもいい」
「違う!」
鳳はまるで自分自身を痛めつけるみたいにしゃべった。聞いていられなくなって遮ったら、自分でも驚くくらいの大声になった。
「俺は謝りに来たわけじゃない」
「え……」
「もちろん詫びも込みではあるが……謝るんじゃなくて、撤回するために来たんだ。俺はお前のことを気持ち悪いなんて思ってない」
「……は」
鳳は自嘲気味に口元をゆがめた。見たことのない表情だった。
「なにそれ、無理あるよ。日吉、はっきり気持ち悪いって言っただろ」
「言った。けど思ってはいない」
「……」
「言ってしまったことは本当に申し訳なかったと思ってる。でもあれは本心じゃない」
言ったけど思ってはいないなんて、自分でも無理のある言い分だとは思う。しかし他に説明のしようもなかった。それだけが事実だからだ。
「……日吉は本心で思ってもいないのに、人を傷つけるようなことを言うヤツじゃない」
「違う。あれは本当に」
「いいよ、もう……日吉は何も悪くないじゃん。気持ち悪いと思われて当然だって、自分でも思うもん」
乾いた声に、うんざりしたようなため息が続く。こいつは三か月間ずっと——もしかしたらもっと前から——そんなふうに考えていたんだろうか。自分は気持ち悪いと思われて当然の人間だ、なんて。
「俺だって、もし同じ立場だったらきっとイヤだと思う。友達だと思ってた相手が、友達のフリをしながらずっと、その……」
鳳はそこで口ごもり、やがて開き直ったように続けた。
「——友達のフリをしながらずっと自分に欲情してた、とか。絶対イヤだよ、相手が好きな人でもなかったら」
「でも俺はイヤじゃなかった」
「……」
あの合宿所で告白めいたことを言われた瞬間から今まで、俺はただ戸惑っただけだった。青天の霹靂みたいな出来事に戸惑いこそすれ、気持ち悪いとかイヤだとか感じたことはなかったのだ。第三者である財前が「正直、俺ならキツい」と言うのを聞いて苛立ちさえ感じたほどに。
「考えてみればたしかに、お前が言うように気持ち悪いとかイヤだとか思っても不思議じゃなかったのに。お前が律儀に着替えのタイミングをずらしてるのだって、べつにそこまで気にしなくていいのにって思うだけだった」
こうやって言葉にしてみると、問題はあまりにも単純だ。——鳳の言う通り、こんなこと相手が好きなヤツでもなければ絶対にイヤなのだ。
「無理にフォローしてくれなくていいよ。っていうか、むしろちゃんと拒絶してくれないと諦めがつけられないし」
「……お前、なんでそこまで卑屈なんだ」
「なんでだよ、どこも卑屈じゃないじゃん。……がんばって日吉のこと忘れなきゃって思ってるんだから、もう優しくしないでよ」
すねて聞く耳を持たなくなった子供そのものだ。鳳はすっかりふさぎこみ、その様子を見ていたら俺の胸には怒りが芽吹いた。本心でないとはいえ「気持ち悪い」なんて言ってしまった自分が悪いのは百も承知だが、「忘れる」だの「諦める」だの「もう友達でいられない」だの、鳳の言葉はどれも勝手だ。そこに俺の意思は微塵も入っていない。——そもそも三か月前のあの日から、こいつはどうして当然のように俺に拒絶されるものだと決めつけているんだろう。
エスカレーター式の学校に通っていたって、小学生の頃からここまで密な付き合いが続いている相手はそう多くない。一学年の人数が多いと、クラス替えとともに縁が切れてしまうことが大半だ。俺は付き合いのいいほうでもないから、放課後や休日にまでお互いの家を行き来したり、稽古事の発表会に招待したり招待されたり、わざわざ誕生日プレゼントを渡したりするのだって本気で好もしく思っている友人だけだ。それに何より先輩たちの代には存在しなかった“副部長”というポストを跡部さんから提示されたとき、素直に頷いたのはそれが他の誰でもなく鳳だからだった。俺だってあなたと同じように一人でも部を率いていけます、とか張り合う気にはならなかった。きっと自分の隣にはあいつがいたほうがいいんだと思った。あいつは俺にできないことができて、俺はあいつにできないことができるから。
——俺はそれだけ信頼しているのに、鳳はたかが一回の告白ごときで友情が壊れるとでも思ったんだろうか?
「……お前さ。ちょっと自己憐憫が過ぎるんじゃねーか」
「えっ……なに?」
俺の気持ちを見くびって信頼を疑ったようなものなのに、自分ばかりが悲劇のヒロインみたいな顔をしている鳳に腹が立った。三か月前のこいつが「全部なかったことにする」なんて言わなければ、俺だってもっと早く自分の気持ちに気づけていたかもしれないのに。
俺は立ち上がってテーブルの向こう側に回り、ベッドのサイドフレームにもたれて座っている鳳の横に腰を下ろした。鳳はあとずさって逃げそうな気配を見せたが、両手で肩を押さえたら縛りつけられたように動かなくなった。
「なっ、なんだよ」
「俺はお前のことを気持ち悪いなんて思ってない。お前はいつも他人を信じすぎていて危なっかしいくらいだが、俺の言葉だけは疑うんじゃねえ」
「……でも、だって、」
鳳はなおもふてくされた様子で口をとがらせた。その頬をひっつかんで、声の出口をふさいでしまう。一瞬だけ唇を触れ合わせて離れる。
言葉でどう伝えても聞き入れてもらえないんだから、行動で示すしかない——そう考えて動いたときの自分はあくまでも冷静だったのに、キスをした瞬間から一気に鼓動が速まって数秒で呼吸も苦しくなった。唇にふれた熱と柔らかな感触を愛おしく感じすぎて胸の奥が痛いくらいだ。気持ち悪いなんて、万にひとつも思うはずがなかった。
「……こっ、これでもまだ疑うかよ」
「……」
「おい、なんか言え」
「……」
鳳は照れるでも動揺するでもなく、思考機能そのものが頭からすっぽ抜けたかのような間抜け顔で固まっていた。きのう鳳にチョコを渡したヤツらはこいつのこんな顔なんて見たことがないだろうなと考えたところで、ようやくその口が動いた。
「な、なに。いまの」
「何、って……」
「……」
「……何を言ってもお前が信じねーから、行動で分からせるしかないと思っただけだ」
「……」
しつこく続く沈黙。さすがに合意を確かめずにこんなことをするのはマズかっただろうかと今さら不安になった俺の耳に、日吉、と呼びかけが届く。
「今の、もう一回できる?」
鳳はこの期に及んでなお懐疑の目で俺を見た。俺は乞われるままに唇を寄せた。勢いに任せてしまったさっきの一回目よりも慎重に、長く。そっと優しく押し込んで、舌先で表面を湿らせて離れた。鳳はまだ呆然としていた。
「五十回でも百回でも構わねーけど?」
「う、うそだ……」
「本当だ」
「……じゃあ、ほんとに百回やって」
「ああ」
顔を近づける。三回、四回、五回……と繰り返す。キスは回数を重ねれば重ねるほど、どこからどこまでで一回と単純にカウントすることができないものになっていった。はじめ緊張気味にこわばっていた鳳の体はいつしか脱力し、俺の背に腕を回して体重をあずけてきた。
「……ん、っ……」
鳳は息継ぎのたびに声をもらし、その声と吐息は徐々に甘い気配を帯びていった。唇と唇でくっついては離れ、くっついては離れるたびに弱い水音が鳴った。昨日から——帰り道で抱きしめられた瞬間から——体の中で燃え続けている火がさらに盛った。
「ひっ……日吉、もう——」
息継ぎの一瞬。最後まで聞き終えるより早く、俺の腕は鳳の体を床に押し倒していた。「わっ」と眼下で声がして我に返る。
「わ……悪い、痛かったか」
「痛くない、けど……」
鳳の目からはようやく懐疑の色が消え、頬は赤く上気していた。頬を撫でると幸せそうに目が細められ、その幸福感はそのまま俺の胸にも注いだ。
なめらかな肌の手触りを感じながら、あおむけになった体に覆い被さる。キスを続ける。鳳の目元には恍惚の色がさし、俺はもっと早くこうしていればよかったと後悔する。——曇った表情を見るのが辛かった。笑顔でいてほしいと思った。俺の手ひとつでこいつがこんなに幸せそうな顔をするなら、もっと早くふれていればよかったんだ。
「何回目だ、今」
「わ、わかんない……。三十回くらい?」
「じゃ、あと七十回だな」
「えっ……も、もういいよ! 俺もう十分だから!」
「よくない。ちゃんと百回やる」
男なら有言実行だ。鳳は抵抗の気配も見せたが、気配だけだったので無視して続けた。途中で舌も入れた。鳳はあからさまに動揺していたけれど、やがて俺の動きに呼応し始めた。舌先を擦り合わせたり舐め合ったりしていると口の端からは唾液が流れた。組み敷いた体が荒い呼吸のために上下する動きが服越しに伝わってきた。猛烈な食欲にも似た衝動のままにむさぼって味わって、回数を数える余裕なんてなかったけど、たぶん百回は超えただろう。さすがに息苦しくなって体を離したとき、俺も鳳も全身に汗をかいていた。重なった体と体のあいだに湿った熱気がこもり、一年でもっとも乾燥する時季であることが嘘のように蒸し暑かった。
はぁ、はぁっ、と切れ切れの息が首にかかる。俺の両肩をつかんでいた鳳の手が、力を失ったようにくたりと床に落ちる。顔は真っ赤で、目元は涙でぐしゃぐしゃになっていた。ここからさらに百回でも余裕だと思ったけれど、俺には先に言うべきことがあった。
「順番が前後したけど、その……俺もお前が好きだ」
「……」
「まだ疑うのか」
「いや……」
鳳は細い声を出し、手の甲で目元をぬぐいながら続けた。
「ここまでされたらさすがに疑いようがないけど……。でも、だったらどうして昨日、あんなふうに言ったんだよ」
「それは……」
「それは?」
「……お前に抱きしめられたとき、気持ち悪いともなんとも感じなかったんだよ。だからつい気持ち悪いとか口走っちまって……」
「……いやっ、まったく意味がわからないんだけど!?」
鳳は困惑をあらわに声を張った。自分でも矛盾していると思うが、他に説明のしようがなかった。
お前は俺のことを本当に友達だと思っているのか——と聞くつもりだったけれど、あのとき俺の体を抱きしめていた鳳の目を見たら聞かなくても答えがわかってしまった。そして欲情の色をはっきりと映したその目で見つめられても、自分は気持ち悪いとかイヤだとか思わなかったのだ。それどころか心地よいとさえ感じていた。
“男に欲情されて喜んでいる自分”は気持ち悪いものなんじゃないかって、あのとき一瞬だけ胸をよぎった拒絶感が矛先を自分自身から鳳にすりかえて出ていった。次の瞬間、俺を見下ろす鳳の悲しげな顔を見て、そんなものは臆病な思い込みだったと気づいたが。
そういう内心を説明した俺の下で、鳳は「じゃあ」と呟いた。すがるような声だった。
「……俺、日吉に触ってもいいの?」
「ああ、構わねーよ。どこでも好きなだけ触ってくれていい」
「ど、どこでも好きなだけ……」
鳳の目に光が宿る。安心させるにしても言いすぎただろうか、一体どこをどれだけ触るつもりなんだと考えたところで、ギュウ、とカエルの鳴き声のような音が聞こえた。
「なんか安心したらお腹すいちゃった……」
と、鳳は照れくさそうに笑って腹を撫でた。
「もしかしてお前、朝食まだだったか」
「うん……朝食っていうか、きのうの夜も食べてないけど」
「えっ」
「誕生日だから家族がいろいろ用意してくれてたんだけど、食欲が湧かなくてさ。日吉、せっかくだからケーキとか食べていかない?」
「……」
はたして自分にそのケーキを食べる資格があるんだろうかと躊躇した俺の横で、鳳は身を起こした。乱れた髪を整えようともしないまま、うれしそうに俺の右手を取る。
「いつもはホールケーキだけど、今年はたまたまピースのやつなんだ。ショートケーキとチョコケーキが一個ずつ残ってるから、どっちも半分こして食べようよ」
「ああ……それはありがたくいただくけど」
「けど?」
「……俺のせいで悪かった。せっかくの誕生日だったのに」
食事もとれないほど落ち込んでいた鳳の様子が家族にまで不安を与えてしまっただろうことは想像に難くない。直接詫びを入れたいくらいだが、こんな事情では謝るのも難しかった。
「日吉のせいじゃないよ、もとはといえば俺が……。まあ、できればもうちょっと早く言ってほしかったけどな。合宿のときからずっと、今日こそ日吉に拒絶されるんじゃないかって思って毎日生きた心地がしなかったし」
鳳は立ち上がり、俺の手を引っぱって廊下に出た。引っぱられるまま一階への階段を下りながら、俺はその背中に言葉をかけた。
「……もっと早く言えばよかったとは俺も思うが、そこはお前にも原因があるだろ」
「俺にも?」
「『全部なかったことにする』とか言われたら、こっちだって思考停止せざるをえないというか……。あんな言い逃げみたいな形じゃなくて、返事を求めたりしてくれればよかったのに」
「そんな、返事なんて……。無理だって言われることしか考えられなかったよ」
「そこが解せねーんだよ。これだけ長く付き合ってきて、俺のほうには好意がないとでも思ったのか」
「えっ……」
鳳は立ち止まり、意外そうに目を張った。
「いや、もちろん嫌われてるとか思ってたわけじゃないよ。でもそれはあくまでも友達としての好意だと思ってたし」
「けど、それってまったくの別物ってわけでもないだろ。お前だって、友達だから俺を好きになったんじゃないのか」
「それはそうだけど……」
言葉はそこで途切れ、鳳は俺の手を放した。一階のダイニングに入ると、テーブルにはガラスの花瓶に生けられた大きな花束と未開封のプレゼントの箱が数個置かれていた。
「……ケーキとか持ってくるから、日吉はそこに座ってて」
鳳はそう言ってテーブルを指した。座って待っているとケーキやら料理やらが運ばれてきた。俺の前にはケーキの平皿がひとつ、向かいの席には夕食の残りだろう料理を盛った皿がいくつも並び、鳳は「いただきます」と手を合わせてそれを食べ始めた。
「すげー量だな、それ」
「二食分だからね。日吉も食べる?」
「いや、俺はケーキだけで十分だ」
鳳は俺がケーキを食べ終えるより早く料理を全部たいらげ、メインディッシュに至っては二杯目まで持ってきた。メインディッシュは多分クリームシチュー的な何かだと思われるが、俺の家では絶対に出てこないメニューなので正式な名称がわからなかった。鳳の家の料理はたいていそんなふうだ。
「そういえば、家族はいつ帰ってくるんだ」
「うーん、夜の八時とかじゃないかな。遠くに住んでる親戚の家のホームパーティーに行ったから」
「……それ、お前の誕生日に合わせたパーティーだったんじゃないのか?」
「うん、たぶんね。でもどうしても元気が出なくて、仮病使ってパスしちゃった」
「……」
馬鹿正直なほど実直なこの友人にとって、仮病以上に重い病気が他にあるだろうか。せめて昨日、逃げ帰っていった鳳をそのまま追いかけていればよかった。一晩かけて気持ちの整理なんかしなくても、こいつの顔を見ればおのずと答えは出たはずだったのだ。
後悔を噛みしめる俺の前で、鳳は「でも」と続けた。
「みんなには申し訳ないけど、結果的には行かなくて正解だったよ。日吉と一日中ふたりっきりで過ごせるなんて、どんな誕生日プレゼントよりもうれしいもん」
「え」
「日吉、このあと予定ある?」
「いや、なにも……」
「じゃ、夜まで一緒にいてくれる?」
鳳は澄んだ目で俺を見た。
俺の答えはひとつしかなかった。
***
食事のあと鳳は皿を洗い、洗濯機から俺の服を取り出して室内に干し、歯磨きを済ませると、また俺の手を引っぱって二階のベッドに入った。何をされるのかと若干身構えたが、鳳はただベージュ色の毛布にもぐりこんで本来の用途でベッドを使おうとするだけだった。
「もしかして寝てないのか、きのう」
「や、寝たよ。三十分くらいは」
「どう考えても寝たうちに入らないだろ、それ」
「……日吉、俺が起きるまでずっとここにいてくれる?」
「ああ」
「絶対だからな」
ピ、とリモコンの音が鳴って部屋が暗くなった。鳳は毛布の端を持ち上げながら俺を見、視線で促された俺はその中に入った。俺の身は熱い腕に囲い込まれ、花みたいに甘い匂いと暖かさが全身を包んだ。濡れた髪のまま寝そべってしまったことに遅れて気づいたが、鳳は気にする様子もなくその髪を撫でていた。
「いやじゃない?」
不安そうな声だった。百回キスしても足りないのかと呆れたが、一方で自分の責任を思い出さずにもいられなかった。だけど鳳の顔を撫で返すために手を伸ばしたのは、決して責任感のためではなかった。透明感のある白い頬は、見た目と同じくらい手触りも優しかった。鳳はうっとりとした顔でため息をついた。
「夢みたい。昨日はここでずっと泣いてたのに」
鳳は毛布の下で俺をぎゅっと抱きしめ、体を密着させてきた。夢じゃないことを確認するみたいに。厚い胸板に頬がこすれ、ふれあった爪先はお互いの脚を絡め取った。心臓の鼓動が速くなり体じゅうの血が躍った。今すぐこの男を自分の下に組み敷いたりしたくなってしまった。
「日吉、耳が真っ赤になってる」
「な、なってねえよ」
「なってるよ。かわいい……」
鳳の指先が俺の髪をかきわけ、熱くなった耳をゆっくりとなぞっていく。毛布の下で、腿のあいだに鳳の脚が入ってくる。
「……いいからさっさと寝ろよ。目の下にクマ、できてたぞ」
「ん」
よほど睡眠不足だったんだろう、鳳はふにゃふにゃした声で「おやすみ」と呟くと、俺にしがみついたまま眠りに落ちていった。俺は寂しがり屋の幼児の抱き枕にでもされた気分だった。だけど実際は幼児どころか並みの大人よりも体格のいい男だから、鳳が身じろいだり寝息をついたりするたびに俺はいちいちドキドキさせられなければならなかった。抱き枕に徹し続けるにはかなりの精神力を要した。
五、六年前にもこのベッドで一緒に寝たことがある。放課後にこの部屋で遊んでいたら天気が大荒れになり、歩いて帰るのも危険だからと泊めてもらった日のことだ。客用の布団も用意してくれていたのにどうしてベッドで寝ることになったんだったか——おぼえていないけれど、たぶん鳳が甘えてきたんだろう。
鳳はあのときも今みたいにくっついてきて、俺はやっぱりドキドキしていた。手をのばしてその温かな体を抱きしめたら、自分の腕の中に収まった友人を守りたいような慈しみたいような気持ちで胸がいっぱいになった。月日がすぎ、二人で横たわったベッドが狭くなっても、俺の胸に去来する感情は同じだった。
次のページへ▶
(※次ページはR18)